『秀山祭九月大歌舞伎』中村吉右衛門が語った『俊寛』の最後にみる景色

中村吉右衛門 2018年『秀山祭九月大歌舞伎』合同取材
1948年(昭和23年)の初舞台から70年。歌舞伎俳優の二代目中村吉右衛門が、2018年9月2日に初日を迎える『秀山祭九月大歌舞伎』(歌舞伎座、~26日千秋楽)に向け、合同取材会で意気込みを語った。
初心に帰る、11回目の秀山祭
「秀山祭」は、初代吉右衛門の芸と精神を受け継ぐべく、2006年9月にはじまった興行だ。吉右衛門は取材会で、今年も開催できる喜びと感謝を述べた。
「11回目ということで、また1から、初心にかえり、初代の芸を見直す気持ちで演目を選びました。多彩な顔触れと、多彩な狂言がそろいます」
そして、長らく舞台から遠ざかっていた福助が、昼の部『金閣寺』で舞台に復帰することに触れ、「私にとって誠の慶事」と喜びを口にした。
「それというのも初代吉右衛門は、五世歌右衛門さんと大変親しくさせていただき、見守っていただきました。私自身は六世歌右衛門のおじさまに色々お芝居を教わり、神谷町の芝翫(七世)の兄さんにも多くの教えを受けました。私はことさら成駒屋のお家に、親近感をもっている男でございます。今回福助さんが、秀山祭で復帰されることに、何かご縁があったのかなと。ご子息の児太郎さんには、その狂言の中で持てる力、才能を発揮し、秀山祭をさらに盛り立てていただければ幸いです」
庶民の味方の悪人の生きざま『河内山』
昼の部『天衣紛上野初花(くもにまごう うえののはつはな)』より、『河内山』は、河竹黙阿弥の作品。吉右衛門は、主人公のお数寄屋坊主、河内山宗俊を勤める。お数寄屋坊主は、江戸幕府の職名ひとつで、茶室に関わる職務につく者だが、現代の感覚のお坊さんとはまったく別。にもかかわらず河内山宗俊は、上州屋のため(そして二百両のため)に一肌脱ぎ、高僧に扮して大名の屋敷に乗り込んでいく。
「『河内山』は講談が元の、どなたにも喜んでいただけるお芝居です。それを立体的にお見せする以上、つまらない『河内山』にはできません。巨悪に対する、庶民の味方の悪人の生きざまが描かれた作品です。皆さんに喜んでいただき、最後には留飲を下げていただけるよう勤めます」
興行によっては「松江邸 広間の場」から上演されることもある『河内山』。今回は「広間の場」の手前のエピソード、「上州屋質見世の場」から上演する。その理由を、次のように説明した。
「『質見世』からやることで、お客様には、なぜ河内山宗俊が屋敷に乗り込んだのか分かっていただける。尚かつ、お数寄屋坊主から高僧に化ける面白さも感じていただける。そのため初代は『質見世』を必ずつけておりました。私もそれに倣っております。初代はもっと面白くやっていた! と、言われるのは分かっておるのですが、難しくてなかなか(笑)。少しでも近づけたらと思いつつ勤めております」
『俊寛』で感じる、初代の魂
夜の部『俊寛』は、近松門左衛門の浄瑠璃『平家女護島』全五段のうち、二段目にあたるエピソードだ。吉右衛門は、主人公の俊寛僧都(しゅんかんそうず)を演じる。
『俊寛』の舞台は、鬼界ヶ島。俊寛(吉右衛門)は、元は都の僧だったが、流人としてこの南の端の孤島にいる。康頼(錦之助)と成経(菊之助)も同じ境遇だが、成経は、海女の千鳥(雀右衛門)と恋仲になり、夫婦の契りを交わす。そこに都から赦免船がくる。康頼、成経、俊寛と千鳥の四人は喜ぶが、許可が下りたのは三人のみ。乗船を拒否された千鳥は嘆き悲しむ。俊寛は、都からの使いを斬り、その罪で自身は島に1人残り、代わりに千鳥を赦免船にのせてやるのだった。ラストシーンで俊寛は、大きな岩の上によじ登り、三人を乗せた船をいつまでも見送る。一人残され、悲壮感とともに茫然と佇むところで幕切れとなる。
「歌舞伎としては、長らく上演されていなかったものを、初代があそこまで練り上げました。播磨屋、初代吉右衛門の魂がこもった芝居です。大切に大切に、やらせていただきます」
吉右衛門は、本作について「竹本(義太夫節)」と「心理描写」の2点から語った。
「『俊寛』は、竹本さんにのってやる芝居です。踊りではない、でも踊りのように体を動かさねばならないところが多くございます。播磨屋は、あくまで竹本というものを大事に、文楽を大事に。そこが大変重要なポイントです」
また、心理描写については「とても現代的」と吉右衛門。「心の動きを大事にやる、という型」がついており、「竹本の三味線と息が合わないとできない型」にもなっているのだそう。
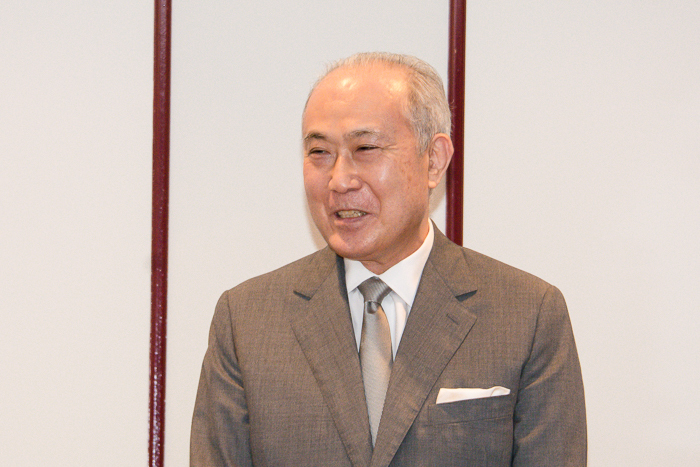
中村吉右衛門
独自の解釈は、弘誓の船から
「俊寛は、養父(初代)の当り役ですが、実父(初代白鸚)もやっておりました。実父には『最後は石のようになれ』と言われました」
そう語る吉右衛門だが、自身の解釈を反映させる一瞬もあるという。島に一人残された俊寛が、岩の上から、三人の乗る船をいつまでも見送るシーンでの、ある経験がきっかけとなった。
「10年、20年前だったでしょうか。最後の場面で(客席の方を見て)船を見送っていると、視界の上の方から、何かがフッとおりてきました。弘誓(ぐぜい)の船では、と思われるものが見えたのです。想像か錯覚によるものでしょうが、私にはそれが俊寛の状態に合っていると感じました。弘誓の船が来る。それは、そのまま死んでいくという意味にもとれます。実際はそうではないかもしれませんが、この芝居におけるは俊寛は、幕の裏で息絶え、解脱し昇天していくのではないか。それ以来、幕が閉まりきる寸前に、ふっと弘誓の船を見上げるように演じています」

劇中で、俊寛は30代から40代の設定だ。「おじいちゃんのようですが、よくよくみれば白髪もありません」と吉右衛門は説明する。若い頃から演じてきたこの役について、今と昔で捉え方の変化があったかを聞かれると、「ありますあります」と即答。
「若い頃は自己犠牲の気持ちが難しかった」と続ける。
「恋こがれる妻の東屋が殺されたと聞き絶望し、仏心でしょうか、若い人に夢を託し、千鳥を船にのせる決断をする。"思い切っても凡夫心“と浄瑠璃にもあり、その言葉で追いかけ、大変に執着をもって遠ざかる船を見送る。それをどこで諦めたらいいのか、どうしたら最後に、石のごとく見送るだけになるのか。若い頃はたぶん演じ切れていませんでした」
「舞台セットの岩は、実際にとても急な階段で、最近では岩に上るだけでも息がきれ、上りきった時には欲も得もなくなります(笑)。若い頃に比べると体力はありませんが、弘誓の船をみる思いで演じる今の方が、近松の書いた俊寛に近いのではないでしょうか。初代は、魂で芝居をする人でした。魂で芝居を、と口でいうのは簡単ですが、やるのは難しい。実父に教わったこと、実母にダメを出されたことも思い出しながら、一から『俊寛』をやってみようと思います」
初代の仕事を次に伝える『秀山祭』
1954(昭和29)年に、養父である初代が亡くなった。新聞か雑誌かの対談で「吉右衛門は止め名にしたほうがいいのでは」というやりとりがあるのを目にしたという。当時すでに初代の養子となり、初舞台もふんでいた吉右衛門は、「自分が継ぐのはどうなのかな?」と悩む時期があったと明かす。
1967(昭和42)年に二代目を襲名し、半世紀が過ぎた。今や説明不要の、現代の歌舞伎を代表する俳優となった。年齢を重ね、体力的に厳しくないのだろうか。
「年齢ですから、ダメな時はダメでやるしかない。芝居が休みの月はだめですね。舞台に上がっている方が、キリっとします。福助くんも舞台に出て、とてもいい方向に行くものと期待しています」と力強く答えた。
「今こうして、秀山祭についてお話できるのは、先人、諸先輩のご指導のおかげです。初代の仕事を次に伝え続けていきたいです。初代には全然足りませんし、初代のやった数々の役も、まだ全てはやれておりませんが、色々な方が舞台に華を添えてくださる中で、なにか新しいことはできないか、とも思っております。そして日頃より申しておりますが、私の目標は80歳で『勧進帳』の弁慶を勤めること。そのゴールインを目指し、走っております。持って生まれた美しさや、芸の才能がある方は、たくさんおられますので、いつも自分はダメだなという思いでやってまいりましたが、それでも初代の魂、やりたかった道への階段は、一歩一歩のぼれているのかなと自負しております」
『秀山祭九月大歌舞伎』は、9月2日から26日まで歌舞伎座で開催される。走り続ける二代目が、初代の魂を受け継ぐ公演。9月の歌舞伎座で、二代目吉右衛門と視線を重ね、俊寛の最後の景色をみてほしい。

※写真の無断転載禁止
取材・文・写真(一部)=塚田 史香
公演情報
『秀山祭九月大歌舞伎』
■出演:中村吉右衛門、中村梅玉、坂東玉三郎、中村雀右衛門、中村福助、松本幸四郎、尾上松緑、尾上菊之助 ほか
※中村梅玉、中村福助、尾上松緑は昼の部のみ、坂東玉三郎、中村雀右衛門、尾上菊之助は夜の部のみ出演