FINLANDS塩入冬湖とそのアートワークを10年以上手がける大川直也が対談で紡ぐ音とアートの「放熱」に迫る

FINLANDS / 塩入冬湖、大川直也
FINLANDSの、新体制になって初のフルアルバム『FLASH』が3月24日に発売された。アルバムとしては約2年半ぶりとなるこの作品には、「2019年は一人なってそれはそれで大変だったし、2020年はコロナになってそれはそれで大変だったし、一人になってからの変化を感じる暇はなかったかもしれない」という塩入冬湖が、自身と向き合う時間の中で改めてFINLANDSで表現したくなった、伝えたくなったものが詰まっている。そんなFINLANDSの音楽をより印象的なものとして聴き手に届けるのが、これまでその全アートワークを手がけ、10年以上一緒に“作品”を作り続けている大川直也氏だ。音楽とアート。切っても切り離せない関係のこの二つは、どのように交差し、二人の脳内で融合し、放熱しながら我々ユーザーの心に届くのか。二人へのインタビューから紐解いてみた。
――FINLANDSの音楽を、さらにユーザーの想像力をくすぐるような“作品”としてどのように2人で作り上げているのしょうか?
塩入:FINLANDSに関してはずっと大川さんにお願いしていて、私が一番最初にアルバムを作った意図やその意味を説明するのは、絶対大川さんです。
大川:音をもらって聴くといくつかイメージが浮かぶので、浮かんだイメージと本人からの話を元に、なぜ僕がそういうイメージを受け取ったかのかと、今回のアルバムはこういうものなんだという本人の言葉の先にあるもの、奥にあるものを擦り合わせる作業です。
塩入:大川さんに音源と歌詞を送る時が一番緊張します。ちょっと違うかもしれないですけど、父親に彼氏を紹介するのってこういう気持ちなんだろうなって(笑)。これは最初から変わらない感覚で、この人が大丈夫って言ってくれれば、きっと大丈夫なんだろうなって思える。すごく薄っぺらい言葉になりますけど、自分の感性って自分ではわからないじゃないですか。でも大川さんがこういうところがすごいいいと思うって言ってくれれば、よかったって思えるし、その逆も然りで、指針的な部分ではあります。

FINLANDS / 塩入冬湖FINLANDS
――その時、すでに塩入さんの頭の中には映像やジャケットのイメージやアイディアがあって、それを大川さんぶつける感じですか?
塩入:大川さんがアイディアを出してくれるのですが、それが突拍子もないことだったり、絶対できないだろう、お金がいくらあっても足りないだろうっていう提案だったりもします(笑)。そこから自分の中で想像していくこともありますが、私からこういう風にしたいんですって言うことは一切言いません。もう全幅の信頼を置いているので。『FLASH』のジャケ写も最初は「トゲトゲ」って言っていて、トゲトゲといえども、どの程度のトゲトゲだろうって思いました(笑)。でもトゲトゲっていうシチュエーションを説明されると、すごくときめくものものだったので、やっぱり見たこともないトゲトゲができ上がってきて。そういう大川さんの発明力というか、何もないところからときめくものを作っていく力、ひらめきってすごいなって思いますね。
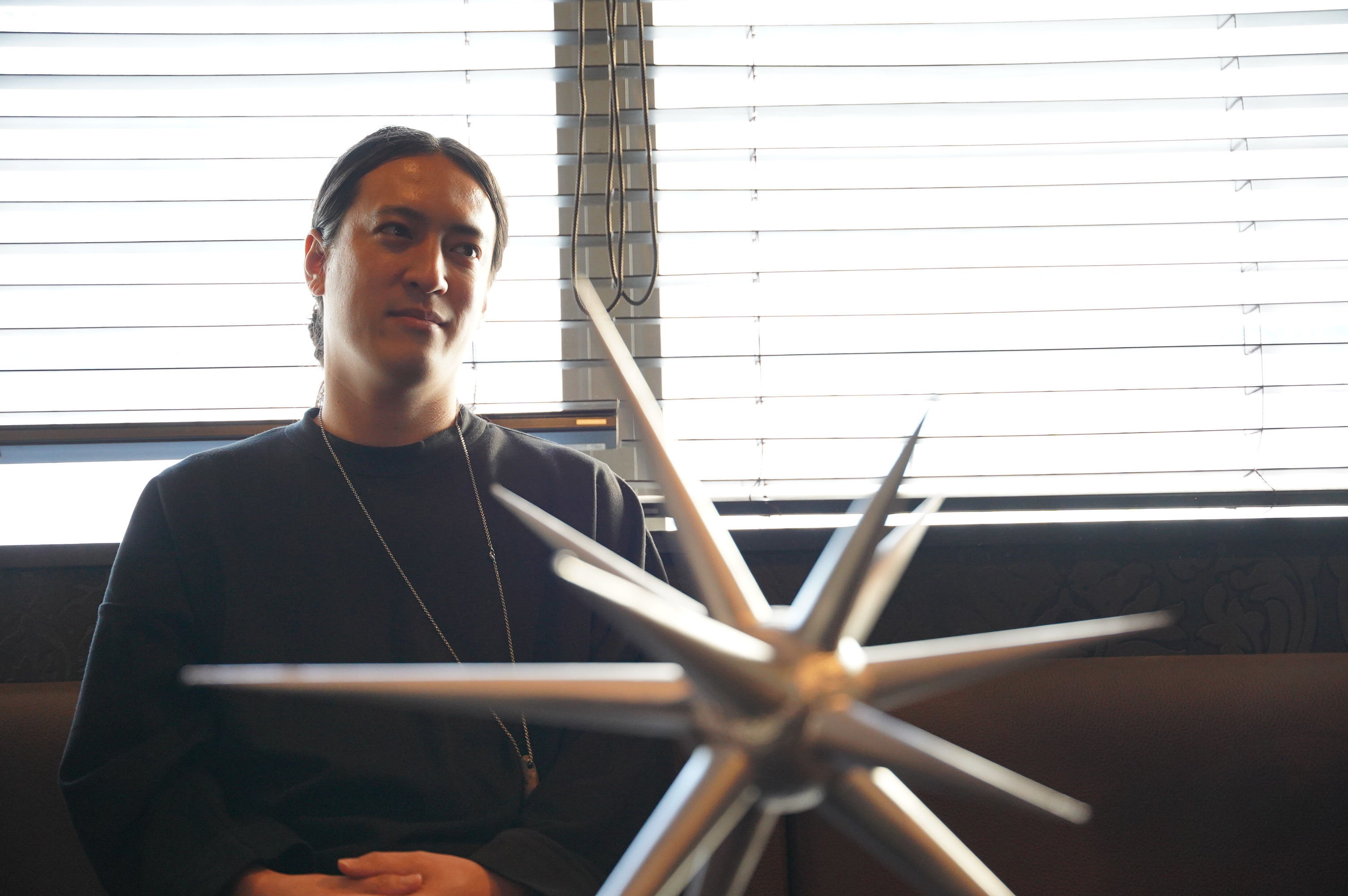
大川直也
――そこは塩入さんの言葉、メロディに誘発される、ということですよね。
大川:もちろんです。
――大川さんもバンドをやっていたんですよね?
大川:ちょっとだけ音楽を(笑)。
塩入:大川さんとは、最初は地元のバンドの先輩として出会って、すごくカッコいいバンドでした。FINLANDSの前のバンドの2作目の音源を作る時に、大川さんが「俺にジャケットやらせてよ」って言ってくれて、その時に大川さんが「例えばこういうダサいジャケットだったらめっちゃ嫌だから」ということを言っていて、この人、私の音楽にこんなジャケットは嫌だ、という想定のデザインまで見えているなんてすごいって思いました。それまで私の周りにはそんなことを言う人がいなかったので、ビックリしました。
大川:それはずっと持っています、こういうのは嫌だという感覚は。
――やはり曲を作って歌っていたという原点があるから、FINLANDSの音楽に対しても、違う角度から斬り込める感じなのでしょうか?
大川:そう信じたいです。
彼女は一年生きたらその一年分のものが、音楽にちゃんと反映されていると思います

FINLANDS / 塩入冬湖、大川直也
――FINLANDSとの出会い、最初に音楽を聴いた時のことは覚えていますか?
大川:ハッキリ覚えています。FINLANDSの前身バンドThe Vitriol(ビトリオル)のライヴをライヴハウスで見て、それがあまりにすごかったので、ライヴハウスの階段で冬湖に話しかけました。
――何年前ですか?
大川:14年前です。でもライヴのクオリティは今同様、凄かったです。
塩入:話しかけてくれて、すごく嬉しかったんですよ。まだ自分がオリジナルバンドをやり始めたばかりで、ライブハウスに出たのも2、3回目だったので、褒めてもらったことが嬉しかったことを覚えてます。
大川:当時、他にも高校生バンドは出ていたし、先輩バンドもたくさんいる中で、冬湖のライヴを見て、音楽の才能のあるってこういうことなんだなって驚愕しました。土俵が違うなと思ったのと同時に、こういう曲を高校生の頃から作っていて、それを当然のようにやっているんだ、という驚きはありました。いい音楽を作るというのはこういうことなんだ、こういう人なんだなって。今もその思いは変わりません。FINLANDSの音楽は変わっていない部分と変わっている部分があって、どちらも好きです。最初に受けた衝撃はずっと更新され続けているし、その周りなのか、芯の部分が変わっているのか、どちらなのか僕は判別がつかないですけど、彼女は一年生きたらその一年分のものが、音楽にちゃんと反映されていると思います。そのどんどん変わっている部分も好きです。優しくもなるし、逆に怒りが増幅されていたり。
――大川さんが、FINLANDSのアートワークを手がける上で大切にしていることを教えてください。
大川:例えばMVの制作ではその曲に対して別の解釈や視線、視点を与えるということを常に考えています。そこはずっと変わりません。冬湖のメロディに言葉が乗っていれば、それ以上にこちらが説明することはなくて、逆にFINLANDSのファンの方やリスナーの方、初めて聴く方に対して僕からFINLANDSを説明することはできないし、できるのかもしれないですけど、それだったらしゃべったほうが早いので(笑)。それから前の作品から次の作品までの間に、自分はこんなことをやっていました、考えていましたという部分を、思い切りぶつけるようにしたいと思っています。

FINLANDS / 塩入冬湖
――お互いが一年で成長した部分、得たものを見せ合う場、という感じでしょうか?
塩入:最初のミーティングからそれは始まっていて、でもそれはクリエイターとしてというよりも、人として生活していく中での発言や発明を披露し合って、そこでお互い何かを発見するという時間なんですよね。『BI』のジャケットを作る前に、大川さんが電気作るようになったんですよ(笑)。「俺、電気作るようになった」っていう連絡をもらって、何を言ってるんだろうなって思いましたが(笑)、写真を送ってきてくれたら本当に電気を作っていて。私は電気を作ろうって思ったことがないし、なんでそこに至ったのかということも気になるし、でもそこも含めてきちんと具現化してくれるところが、やっぱり普通の人間からすると考えられないというか。でも作りたいって思ったものを作れるようになるのって、すごく大きい進歩じゃないですか。そういうのがすごく刺激的です。作りたいと思ってなんでも作れるわけじゃないというのは、日々自分で曲を作っていても思うことで、それをやってのける、すごい進歩をあっけなくやってしまうすごさを大川さんには毎回感じています。
――その「電気」=二つの発光体のオブジェがジャケットになっている『BI』のMVは、大川さんが先に映像を撮って、そこに塩入さんが曲を乗せるという、それまでなかった手法でした。
塩入:あの時は映像を見て、本当に感じることが多すぎて感動しました。当時は本当によく会って話をしていたので、映像の最初から最後まで、説明がなくてもその意図がわかりました。MVって例えば撮り方とか、使っている小物の意味とか、私にはわからない意図がきっとあると思います。でも『BI』に関しては、本当に一から十までわかる。少し悲しくなるような部分も、きっと大川さんはこういうところに、愛おしさとか寂しさを感じて、こういうシーンを制作したんだなっていうのが、今までで一番わかった気がします。だからあんなに長い曲でもすんなり書けました。
大川:曲を作ってもらうということがあったし、当時の僕の気分だったのかもしれませんが、余地、そこを解釈できるような余地を残すということは、すごく意識したかもしれません。

FINLANDS / 塩入冬湖、大川直也
――できあがった曲もそれまでとは違う感覚がありましたか?
塩入:自分に合ったものを、というよりこの映像に一番自分が似合うと思うのは何だろうって考えたところが、一番違うと思う。大川さんがどういう意図で作ったのかを考えた時、特に言葉やテンポの関しては似合うか似合わないかということをより考えました。あの曲は映像を観ながら聴いた方が、より鮮度が高いものとして、何かを感じてもらえると思います。
大川:ちょっと劇伴ぽい作り方というか、主題歌っぽいというか映画音楽みたいな作り方になるじゃないですか。人が作ったものにインスピレーションを受けて何かをする時は、自分一人でものを作る時より、少しだけ優しくなると思うんですよ。作った人のことを思うし、僕もジャケットを作る時はそうだし、届く人のことを想定すると思うので、そこの“優しくなる成分”がすごく美しい曲だなと思いました。もちろん世の中には出ない自分だけのために書いた曲も美しいと思うし、この人だけに聴いて欲しいとか、これくらいの人に聴いて欲しいとか考えると、その時に出る色々な優しさの成分があると思います。ミュージシャンは人のものに対して曲を作るってあまりないシチュエーションだと思うので、そういう時に滲み出る優しさのみたいなものが、すごく好きです。
本当にそう思います。エネルギーの放出です

FINLANDS / 塩入冬湖、大川直也
――先ほど今回のアートワークのポイントになるトゲトゲの話が出ましたが、これはどういうところから着想したのでしょうか。
大川:ジャケットの話をしている時に、怒りと鬱憤というキーワードが出てきて。怒りにも色々種類があると思うし、別の角度からみると神聖視できるものだと思いました。例えば神の怒りを鎮めるために、昔の人ならば祠を作って、天災が起きたらそれを鎮めるべく祈るし、雨が降らなかったら雨乞いをしましょう、というところから「祭り」って始まっているじゃないですか。それで今回はお祭りじゃんっていうところから話が始まりました。で、お祭りにはご神体が欠かせないし、それでトゲトゲです(笑)
塩入:トゲトゲがご神体(笑)
大川:MVに関してはお祭りのイメージで、例えば江戸時代のええじゃないか騒動とか、破れかぶれになっている状態の赤です。発散のための赤。だから衣装も髪も背景も小道具も全部赤、それ以外の色は使いたくなかった。
――赤が怒りの象徴になっているんですね。
大川:怒りと思っているけど、冬湖の中にはもっと大きなエネルギーがあって、それを発散させましょう、ということです。
塩入:本当にそう思います。エネルギーの放出です。
こちらが制作スケジュールをずらします(笑)

FINLANDS / 塩入冬湖、大川直也
――ジャケットは決め打ちで1パターンだけ提出するタイプですか?
大川:そうです。それまでの成功体験に頼らないというか、前回こういう感じでうまくいったから、ということは一切考えません。全くやり方もわからないという状態から始めます。そうすると勝手に集中力が増すので。トゲトゲのジャケットにしようといったものの、作り方が全くわからなかったので、そこからのスタートでした。
塩入:大体一年半おきくらいにCDを出すじゃないですか。その間に大川さんは新しい武器や手法を手に入れているので。会うたびに色々と選択肢が増えていて、だから前作に倣ってとか、それまでやったことがあるようなものがアイディアとして出てこない。進化を止めた人ならそうはならないかもしれないけど、大川さんはいつもものすごい変化を持ってきてくれます。
大川:ちなみ最近は土面作りにハマっています(笑)。
――もしかしたらそれが次にFINLANDSのアートワークに使われるかもしれない?
大川:いえ、それはもう別件で使いました。
塩入:なんで使うかな…(笑)。
――塩入さんは例えば大川さんが手がけたsumikaや藍坊主のアートワークを見て、すごくカッコイイのを見つけたら悔しいと思うほうですか?
塩入:悔しさはなくて、嬉しいかも。大川さんが関わっているミュージシャンもよく知っている人も多いので、「そうきたかー」って逆に新鮮味を感じます。
――これからも大川さんとのタッグは続きそうですか
塩入:続けたいです。友達であり先輩であり、仕事仲間であり、こういう関係を築ける人って本当にいないなって思っていて。いるかもしれないけど、こうやって共作できる人は他にはいないと思います。ものを作った時に、最後大川さんがアートワークで締めてくれるというのが私の中では固まっています。できればずっと一緒にやっていきたいので、忙しくなっても断らないで欲しいです(笑)。他のアーティストとスケジュールが被ってしまった場合は、こちらが制作スケジュールをずらします(笑)
大川:そんなわけないでしょ(笑)
――FINLANDSが一人体制になると聞いた時はどう思いましたか?
大川:冬湖が作る歌詞、曲のファンだったし、(コシミズ)カヨのベースのファンだったのでショックでした。やっぱりカヨのベースとコーラスって凄かったんです。そういう武器さえなくなった状況でどうなるんだろうって思ったし、もちろん寂しさありましたけど、楽しみの方が大きかったです。
塩入:一人になるんですって言った時に、他の人は大体「大丈夫?」みたいな感じのことを言ってくれるのですが、大川さんには「落ち込んでる?」って聞かれて。そうやってストレートに聞かれると、いや、正直落ち込んではないかもとか思って。肚が決まっていたというか、落ち込んでいるムードに、私が勝手に追いやられていただけなのかもって思いました。自分は別に落ち込んでないかもという事実に、大川さんからの率直な問いがあったから気付けたと思います。感情の中にもある程度テンプレートってあるじゃないですか。こういうことがあったら悲しまなきゃ、落ち込まなきゃ、ちょっと立ち止まらなきゃ、みたいな感じが。そういう時に大川さんに「なんで?」とか、「楽しいじゃん」と言われた事で、「そっか」って気付かされました。大川さんも独立して一人で仕事をすることになった時「武者震いがするくらい楽しみ」って言っていて。当時の私からすると、自分ひとりで全てを背負ってやっていくのは怖いことだと思っていました。でも大川さんの言葉が年々わかるようになってきました。絶望的な状況というか、人間本当にひとりでこれから進んでいくというタイミングで、ワクワク感を感じられる人はあまりいないと思います。そういう状況に陥る人もあまりいないし、だから特権だったんだなって思えるようになったし、気づかせてもらったということを、一人になった時にやっとわかりました。
取材・文=田中久勝 Photo by 菊池貴裕