細田守監督と宇垣美里が語る、高畑勲作品の魅力 『高畑勲展』スペシャルトークをレポート

東京国立近代美術館で現在開催中の『高畑勲展─日本のアニメーションに遺したもの』。連日多くの来場者を集めている本展にて、スペシャルトーク「細田守が語る監督『高畑勲』」が開催された。この日は映画『バケモノの子』や『未来のミライ』の細田守監督が、高畑作品や高畑監督の演出術についてトークを展開。フリーアナウンサーの宇垣美里を聞き手役に、様々な話題が飛び出した。ここではその中から注目すべき部分を抜粋し、その内容を一部再構成してお伝えする。
キャラクターデザインだけで作品の世界観が伝わる『赤毛のアン』
宇垣:今日初めて本展をご覧になられたということですが、どんな感想を持ちましたか?
細田:先に図録を見ましたが、本物を見るのは今日まで楽しみにしてきました。時間がいつまであっても足りないと感じるほど、高畑監督の軌跡が充実していて素晴らしい展示でしたね。何度見ても新しい気付きがあるような、非常に奥が深い展覧会だと思います。
宇垣:細田監督が特に思い出深い高畑作品は、どの作品でしょうか。
細田:僕が一番好きなのは『赤毛のアン』ですね。『アルプスの少女ハイジ』や『母を訪ねて三千里』にも同じことが言えますが、50話全部で1本の映画を見ているような感じなんです。特にアンは思い出深い作品で、最初の放送をリアルタイムで見ているし、再放送でも見ています。何度見ても見るたびに感じ方が変わるのがこの作品の好きなところ。そういう作品ってそうそうないですよね。

会場に登壇した二人
宇垣:『赤毛のアン』はアンのキャラクターも魅力的。そばかすが印象的で、すごく可愛いです。
細田:最初に見た時からすごく変わったキャラクターデザインだと思っていましたが、今回、近藤喜文さんのスケッチを見て、改めてなかなかないデザインだと思いました。額が大きくて、目の下のくぼみがすごく立体的に感じるように描かれている。それがリアルな存在感を出しているけど、写実的になりすぎずにキャラクターとして落とし込まれているのが凄い。アニメーションでありつつ、リアルな少女の物語という世界観がキャラクターデザインだけで伝わってきます。
『太陽の王子 ホルスの大冒険』と東映動画の思い出
細田:キャラクターデザインといえば、時系列が前後しますが、ホルス(太陽の王子 ホルスの大冒険)のデザインって見ましたか? いろんな方が同じキャラを描いているという。
宇垣:ヒルダの絵ですよね。一人ひとりの思い入れが違って、まだ(作品自体を)見たことがないのですが大好きになってしまいました。
細田:まだ見てないってことは、これから見て楽しめるということですね。いいなぁ、若い人は(笑)。宮崎駿さん、小田部羊一さんら様々な方が描いたヒルダの中で、最終的に森康二さんの案が採用されるんですが、森さんのデザインは人間と悪魔の間で揺れ動く存在感みたいなものが表情にはっきり出ていて、選ばれた理由がよくわかります。その一方で、奥山玲子さんが描いたヒルダもとてもかっこいい。すごく強い女性として描かれていて、本当に素晴らしいです。50年くらい前のキャラクターデザインですけど、今見ても現代的なキャラに見えますよね。
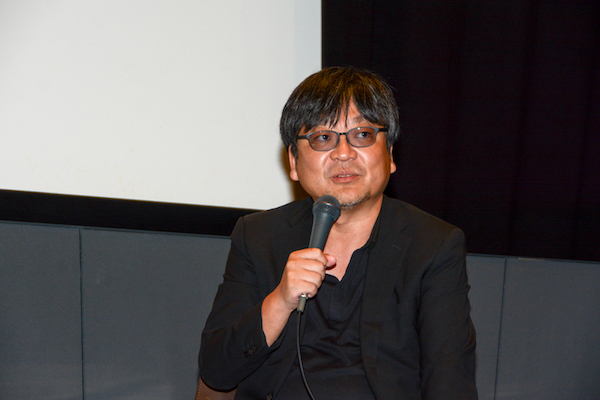
高畑作品への思いを語り尽くした細田守
宇垣:「ホルスの大冒険」は東映動画で作られた作品ですが、細田監督も東映動画に所属されていました。細田監督が感じる東映動画の魅力とはどんなところでしょう。
細田:高畑監督が活躍された当時の東映動画というのは、長編のアニメ映画を作る場所で、「アニメーション作り=映画作り」という意識が高い環境だったと思います。それに比べて僕が入社したのは1991年のことで、当時すでに長編アニメ映画は下火でした。ただ、最初に仕事を教えてくれた角田紘一さんは長編アニメに長く携わっていた方で、よく「細田、アニメーションというのは映画を作ること。長編を復活させることが東映動画の使命なんだ」と言っていた。その中でいつかは映画を作らねばと思ってやってきました。そういう映画作りに熱いスタッフがたくさんいて、様々な試行錯誤を重ねながら長編映画に取り組んできた歴史が東映動画の魅力だと思っています。
宇垣:高畑監督は若い頃の絵コンテもすごく細かく書き込まれている。そういうところも環境からの影響が大きかったのでしょうか。
細田:今の日本のアニメーションは監督中心主義というか中央集権的な作り方が主流です。でも、高畑監督が若手の頃は作り方自体が試行錯誤で、監督も演出助手でありながら、その立場を超えて提案したりとか、一部では監督的な立場も担っていたのかもしれない。僕が入った時にはシステマティックな作り方になっていたので、そういう話を聞くと羨ましい気持ちもある。黎明期の中で試行錯誤するチャンスというのは、その時代の人しか味わえない醍醐味があったのだと思いますね。
アニメにおける美術の力を感じた『セロ弾きのゴーシュ』
宇垣:ここまでは思い出の作品の数々を伺ってきましたが、実は一番語りたい作品は別にあるそうですね。
細田:今回、皆さんにも注目していただきたいのは『セロ弾きのゴーシュ』の背景美術です。僕も実物で見るのは初めてで、とても感動しました。この作品は『母を訪ねて三千里』や劇場版の『銀河鉄道999』で美術監督をされた椋尾篁さんが、ほぼ一人で美術を手がけられている。普通、一人で描くことなんてないのですが、この作品はオープロダクションという作画スタジオが自主制作で作った作品で、普通の作り方ではありませんでした。テレビシリーズの合間を使ってコツコツと作ったので完成までに5年もの歳月がかかっているんです。何が凄いかといえば、アニメーションがリアル主義に偏っていく中で、アニメが絵であることを主張しているところ。一人で美術をやる中でチャレンジを重ねて、こういうタッチを編み出された。それまで日本のアニメーション美術で表現できなかったタッチが、作品全体の世界観になっていった。美術の世界観だけで作品の表現を高みに持っていけることは少ない。今はアニメーションが絵であることを忘れている感がありますが、椋尾さんの仕事はアニメにおける美術の力を思い出させてくれます。

お気に入りの高畑作品は『かぐや姫の物語』と語った宇垣美里
宇垣:細田監督は、ご自身の中に「高畑イズム」のようなものを感じることはありますか?
細田:僕自身は高畑さんの作品で助監督や演出助手をやったことがなく、ジブリに行った時に何度かアドバイスをもらった程度なので、偉そうなことはいえません。ただ、去年『未来のミライ』がカンヌの監督週間に招待されて、公式上映の日が高畑監督のお別れの日と偶然重なった。当然、カンヌでも高畑監督が亡くなったことは話題になっていて、公式上映後の会見などでも高畑さんに関する質問をいくつも受けました。その多くは「高畑監督が亡くなって、これからの日本のアニメーションはどうなっていくのか」というような質問でしたが、そこで僕は「高畑監督が亡くなったからといって、日本のアニメ界は高畑監督の積み上げたものやアニメ作りの指針を失うわけにはいかない」と言いました。そこには高畑監督が問いかけてきたことや形にしてきたことはこれでおしまいではなくて、その問題意識やテーマを誰かが引き継がながなければならないという思いがありました。アニメーションの表現が今のままで終わるのか、もしくはさらに発展するのか、それとも違う力を持つのか、そういうことが今まさに問われている。その中で新しい表現を開拓していく必要があると思っています。

この日は満席となった観衆からも質問を受け付けた
高畑作品のファンを自認する二人のスペシャルトークは、その他にも多彩な話題が飛び出し、充実した90分間となった。本展では、映画監督・高畑勲の足跡を1,000点以上の貴重な資料で紹介。アニメーションの革新に挑んだ高畑勲の生涯に迫っている。約半世紀に及ぶ高畑監督の業績は、いわば日本のアニメーションの歴史そのもの。高畑監督の貴重な直筆資料、アンやハイジのデザインも見られるので、ぜひ足を運んでみてはいかがだろう。
『高畑勲展─日本のアニメーションに遺したもの』は、東京国立近代美術館で10月6日(日)まで開催中。
イベント情報
Takahata Isao: A Legend in Japanese Animation
会場:東京国立近代美術館 1階 企画展ギャラリー(〒102-8322 東京都千代田区北の丸公園 3-1)
会期:2019年7月2日(火)〜10月6日(日)
※( )内は、20名以上の団体料金。いずれも消費税込。
※中学生以下および障害者手帳をご提示の方とその付添者(1名)は無料。
※本展の観覧料で入館当日に限り、所蔵作品展「MOMATコレクション」(4F-2F)もご覧
いただけます。
同時開催:所蔵作品展「MOMATコレクション」(4F-2F)2019年6月4日(火)~10月20日(日)