注目の演出家・眞鍋卓嗣にインタビュー~オペラシアターこんにゃく座『森は生きている』新演出・オーケストラ版に挑戦

眞鍋卓嗣 撮影:Reishi Eguma(C-LOVe CREATORS/YAT)
新しい日本のオペラの創造と普及を目指し、演劇的要素を高めた日本語によるオペラを上演してきたオペラシアターこんにゃく座が、旗揚げから50周年を迎えた。その記念公演第1弾として、芸術監督で座付き作曲家であった林光が遺したオペラ『森は生きている』を上演する(2021年2月19日~2月24日、世田谷パブリックシアター)。
本作は、1992年初演以来、毎年上演を重ねてきた財産演目のひとつで、これまで1992年に岡村春彦、2005年に髙瀬久男、2012年に大石哲史が演出を手がけてきた。そして今回、「新演出・オーケストラ版」と銘打って本作に挑むのは、劇団俳優座の眞鍋卓嗣(まなべたかし)だ。劇団俳優座『雉はじめて鳴く』(作:横山拓也)と名取事務所『少年Bが住む家』(作:イ・ボラム)の演出で、2020年度の紀伊國屋演劇賞個人賞受賞、読売演劇大賞ノミネートなど、今を時めく気鋭の演出家である。そんな眞鍋にリモートによるインタビューをおこなった。
【動画】こんにゃく座 オペラ『森は生きている』2021 告知
―― 眞鍋さんがオペラシアターこんにゃく座を演出するのは3作目になりますね。また、東京二期会オペラ『メリー・ウィドー』の演出や、中島みゆき『夜会』シリーズのステージングなど、音楽関係の舞台のお仕事もされています。元々、音楽への造詣が深かったのですか?
いえいえ、全然です。幼いころにピアノを習っていたとか、むかしバンドをやっていた程度で、取り立てて詳しいわけではないんです。俳優座以外ではまだ仕事がなかったころに、最初に声をかけてくださったのが、こんにゃく座さんでした。なぜ声をかけてくださったかはわかりませんが、結果的に音楽物との相性は良かったようです。
―― バンド経験は、音楽系舞台を演出するうえでのアドバンテージになっているのでは?
バンドといってもメンバーは二人だけでした。当初は普通のバンド編成だったのですが、一人抜け二人抜けで、デビューの時には二人だけになっていた。相方がボーカルをとり、僕がギターを弾くというスタイルです。二人とも作詞・作曲を行ない、バンドサウンドにはこだわっていました。その際に、音で何かを作るとか、どうしたら質感を伝えられるのかといったことを試行錯誤していたので、そういう意味では、当時の経験が何かしら今の自分の強みにはなっているかと思います。オペラの舞台作りでも音楽を聴いていると、風景が浮かんだり、何かの解釈につながるなど、演出の方向性を考えるきっかけが与えられます。

オペラシアターこんにゃく座 稽古場での眞鍋 (撮影:前澤秀登)
■こんにゃく座には「みんなでつくる劇団の魅力」が息づいている
―― こんにゃく座には、どんなところに魅力を感じていらっしゃいますか。
チームワークがすごくいいんですよ。スタッフワークも全員でやりますしね。劇団というものは、所帯が大きくなると演技部は演技部、舞台部は舞台部と仕事が分業になっていきます。しかし、こんにゃく座さんは、みんなでガチャガチャやりながら一緒に作品を作っていく劇団の良さを大事にされている印象があります。しかも音楽をやっているせいか明るいんです。浄化されているというか、清々しい身体になっている。歌うということは、まさにそういうことなのかもしれません。
そして“歌役者”というあり方が素晴らしいですよね。オペラ歌手はどちらかというと「歌手」であることに重きを置いている方が多い印象ですが、こんにゃく座の方々は俳優としての意識をより強く持って、役の心情をしっかり汲み取って歌い、演じている。特に大ベテランの大石哲史さんを拝見していると、しっかりと俳優であり、セリフをしゃべっているように歌われるんですね。僕がこんにゃく座さんとお仕事をやらせていただいているのは、そういうところに惹かれているからでもあるんです。
―― 今年は、こんにゃく座の50周年、『森は生きている』は財産演目の中でも特に大事な作品だと思います。演出にあたり、どんな想いをお持ちですか。
最初に(『森は生きている』の演出を)お声がけいただいたのは3年程前でした。おっしゃるように大事な演目であることは知っていましたから、光栄なことですし、ありがたいお話ですので二つ返事で決めたような気がします。ただ、当初からこうしようというものがあったわけではありませんでしたから、僕が面白いと思えるかどうか、その道筋をどうピックアップできるかに不安はありました。けれど今は、稽古する中でそれがしっかり生まれてきています。
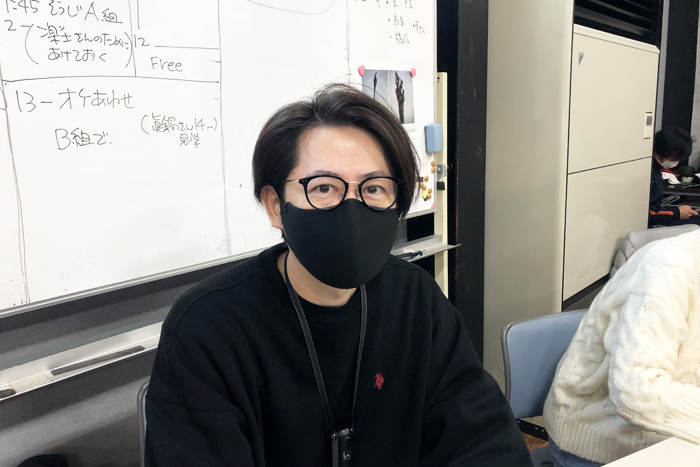
眞鍋卓嗣
―― 「新演出版」として新しい息吹を吹き込んでいるのはどんなところですか?
新しいかはわかりませんが、原作を読み直した時に、現代に通じるものがあったんです。たとえば、女王様の立ち位置、人物造形が気になっています。大晦日にもかかわらず「新年までにマツユキ草を摘んできた者には籠いっぱいの金貨を与える」というおふれを出す女王様はとんでもない人として描かれることが多いと思うんですけど、そうさせているのは彼女を取り巻いている周囲の体質かなと。
―― いわゆる忖度ってやつですね。
女王様といっても14歳、子供らしいわがままさはあると思うんです。でも、森とは共にあるという考え方と対立し、自身との主従関係に置こうとする。その結果として主人公の娘が冬の森にマツユキ草を探しにやられる。
その時にわがままな女王様との主従関係を強調する描き方もあると思うんですけど、そもそもなぜそうなってしまったかと言えば、急に女王という地位を与えられたり、周りからは女王たるものこうあるべきだと言われたり、統制しないとうまくいきませんよと言われたり、あるいは大人の都合に利用されたりということが14歳の一人の子供に降りかかっているとすれば、人間形成に支障をきたすと思うんです。彼女にとっては女王であることが自分のアイデンティティーとなって、命令することがどんどん当たり前になるということが起きるんじゃないかと想像したり。
今回の『森は生きている』を、とりたててそのように描こうというのではないのですが、もし子供たちが見てくれるのであれば、僕に見えている人間社会、人間関係を投影させないのは嘘をついてしまうことになるので、それはしたくないなと思っていますね。主人公の娘のようにどんな境遇や環境でも前向きに生きると良いことがあるってことも含めて。

■劇団の想いや背景を知ると身が引き締まる
―― 森の中へマツユキ草を探しに行かされる少女が出会う「十二月(つき)」の精霊たちが、この作品の見どころですね。
まず、こんにゃく座の皆さんがすごく愉快で、個性的で、温かい方々なんですよ。十二月はそれぞれの季節の特徴を背負ったキャラクターですが、皆さんにはそのまま十二月になっていただければと。前回は精霊っぽく表現されていたようですが、ご覧になったお客様が十二月を見て、また、こんにゃく座の皆さんに会いたいなと思っていただけるようにできたら、という目標はあります。衣裳の山下和美さんが、プランを彼女のお子様に見せて「これはどういう感じがする?」と確認をとって現場に持ってきてくださるのですが、出てくるアイデアが本当に面白いんです。白神ももこさんの振付も含めて楽しい時間になると思います。
―― 演出されるうえで、林光さんの音楽はいかがですか?
僕が語るのは本当に畏れ多いのですけど、素晴らしいです。言葉にしたら陳腐になってしまいますが、奥行きを感じます。ここでどういう寒さを表現したいのか、今はどういう情景が広がっていて、演劇的にはどういうものをピックアップしたいのか、そういう要素がすごく巧みに織り込まれている。視点が豊富ですし、それを表現するあらゆる手法をお持ちだったのだろうと想像できます。だからこそ僕自身もいろんなことを織り交ぜて編んでいかなければいけないと思っています。まずは音楽を理解し、音楽が持っている質感を損なわないように大事にしつつ、一方で自分が進行していきたい演出、裏で流れている心理描写をどう表に起こすかなど、そういうものを全部まとめると見えてくるものがあると思っています。
―― 作品の中で特に刺激を受けたところは?
いろいろあるのですが、1幕の中盤がすごく荘厳な音になっているんです。「森を閉める」という場面なんですけど、じゃあ「閉める」とはどういうことなのか。12月から1月に交代するための下準備をするということなんです。ならば、こちらの方で音楽の荘厳さに合わせて、儀式的に描こうと考えています。
―― 公演に向けた意気込みを改めてお話しいただけますか?
こんにゃく座の皆さん一人ひとりが『森は生きている』を非常に大事にされていることは稽古場でひしひしと感じています。過去に何度も新たな演出で上演されている作品でもありますし、メンバーの皆さんの想いや背景を知ると身が引き締まります。初めてこんにゃく座さんのことを知ったときに、こういう活動をされているカンパニーがあるんだ、日本語だからこそ生み出せるオペラがあるんだということに驚いたことを憶えています。
そういう意味では僕の演出した作品を何年上演していただけるかは、とても気になるところです。稽古場での顔合わせの時、音楽監督の萩京子さんから「今後10年、20年上演できる作品を」とおっしゃっていただき、ドキッとしたんです。もちろんその意気込みをわかって引き受けてはいますが、だからこそ普遍的な部分に焦点を当てて、しっかりと捉えて成功することが大事だと思います。

眞鍋卓嗣
取材・文=いまいこういち
公演情報
ピアノ/入川 舜(A組)・榊原紀保子(B組)
打楽器/高良久美子