ソロ活動35周年の林英哲が見据える「あした」――和太鼓の歴史を変えたリビングレジェンド
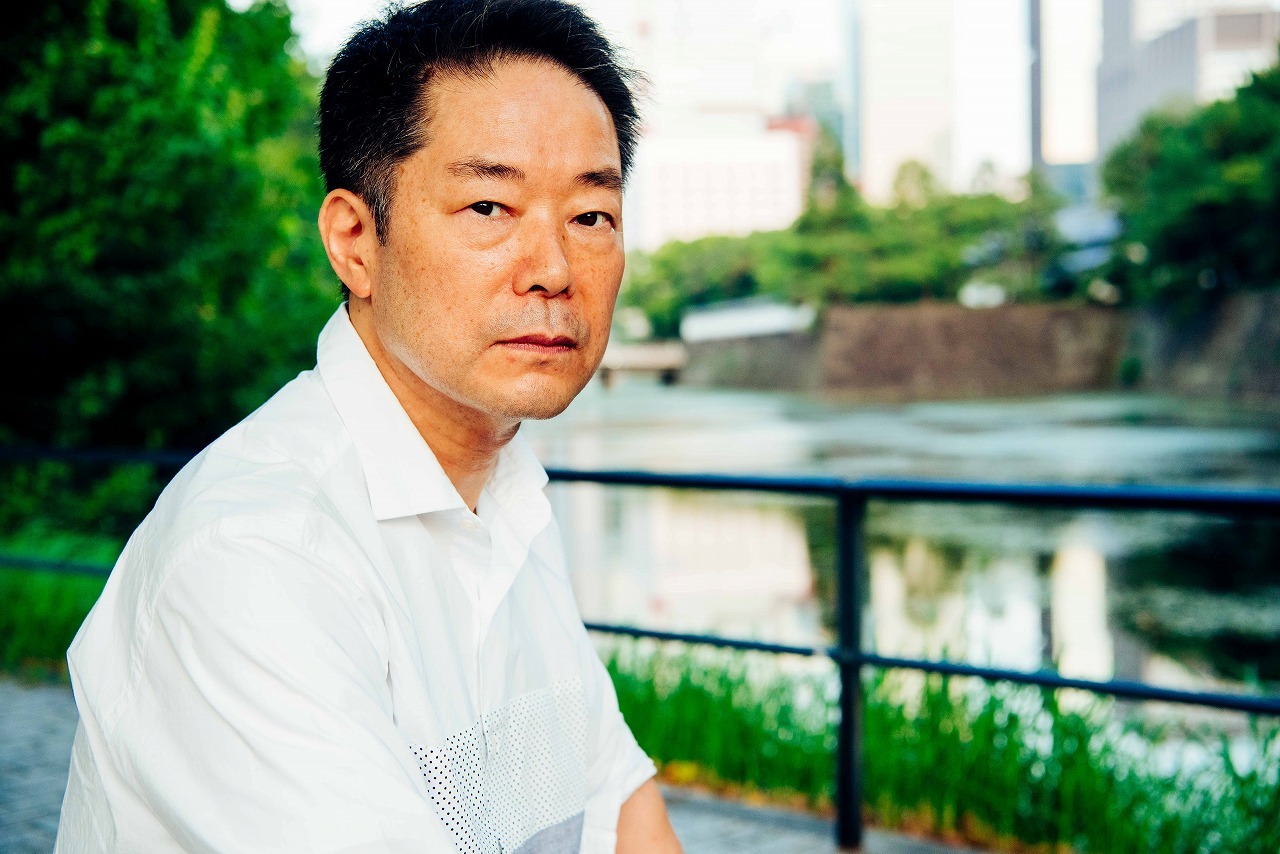
林英哲
大きな和太鼓を一糸乱れぬ動きで叩き続ける、屈強で筋骨隆々な男性たち――こんな和太鼓のイメージは、実のところ1970年代以降にかたち作られていった新しいスタイルなのだということをご存知だろうか。伝統的には、お祭りの伴奏としての性格の強かった和太鼓。その和太鼓自体をメインに据え、アンサンブルやソロの演奏に耐えうるものに昇華させていった立役者、それが林英哲である。そんな“生きる伝説”とでも言うべき林も、2016年に演奏活動45周年を、今年2017年にはソロ活動35周年を迎えた。10月に控える独奏35周年メモリアル・コンサート「あしたの太鼓打ちへ」について、そして65歳となった林がどんな「あした」を見据えているのかを伺った。

林英哲
タイトル「あしたの太鼓打ちへ」に込めた想い
――今回のメモリアル・コンサートのタイトル「あしたの太鼓打ちへ」は、林さんのご著書からとられていますね。どのような公演になるのでしょうか?
僕は伝統芸能から出発していないので、過去のものより常に新しいものをどう作るか、どう伝えていくかということが自分の仕事だと思って活動してきました。これまでの活動を振り返ってみて、その時代時代でエポックメイキングな曲を今回並べているんです。
自分の年齢(65歳)のことも考えると、あと何年できるだろうなっていうのがあるんですよ。そうなると、僕が元気でまだしっかりお手本演奏が示せるうちに出来るだけ、弟子たちのアンサンブル(英哲風雲の会)に、こういう風にやるんだよということを伝えておきたい。せっかく、こういう文化がこの時代に育ったのだから「後は野となれ山となれ」ではしょうがないですよね。だから「あしたの太鼓打ちへ」を今回のコンサートタイトルにしたんです。
――プログラム構成を拝見すると、コンサートの前半はソロと、ゲストである新垣隆さんのデュオが予定されていますね。具体的には、どのような作品を演奏されるのでしょうか?
2年に1回、八ヶ岳高原音楽堂でソロのパフォーマンスをやっているのですけども、去年作った作品のテーマがジョゼフ・コーネル(1903–72)というアメリカの現代美術家でした。彼は自分で絵を描くわけじゃないんですけれど、箱のなかに自分のコレクションを詰めるっていう面白い表現方法をしていて。その作家の人生をテーマに作品を作りました。
コーネルの評伝を読んだら、彼はバレエやオペラ、クラシック音楽がとても好きだったというんですね。なのでクラシックの音楽を箱のなかから聴こえてくるようにしたんです。今回は、そのなかで使った音楽を演奏しようと思っているのですが、今回せっかく新垣さんが出てくれるので僕のソロの間にも弾いてもらおうかなと。
――ソロの部分でお二人の共演があるというのは、それまた面白いですね。
その後、きちんと新垣さんとデュオをやるのですが、NBAバレエ団のために彼が去年作曲した「死と乙女」を演奏します。バレエの上演では音を変えるとダンサーが踊れなくなってしまうので、ひとつも間違えられない。だから結構大変だったんです。でも、今回は演奏バージョンなので、もうちょっと自由にやろうじゃないかということにしています。
――「死と乙女」というタイトルは、シューベルトではなくエゴン・シーレの絵画から来ているとのことですが、どのようにこのテーマが決まったのでしょうか?
ウィーンのレオポルド・ミュージアムにあるシーレのコレクションが僕は大好きで、何回も行っているんですけれど、振付の舩木城さんと「シーレ大好きですよ!」と盛り上がってしまって(笑)。
――昨年、新垣さんと共演された際の印象はいかがでしたか?
あの通りのとってもシャイな方で、普段ほとんど言葉を発しないぐらいなんですけれど、演奏は非常にアグレッシヴにおやりになるので、面白かったですよ。フリージャズっぽいのもおやりになるし、非常にキャパシティの広い方で演奏家としてもとても優れていらっしゃいますしね。だから今回も色んなことに対応していただけるんじゃないかと思って楽しみにしています。でも年齢的には親子ぐらい?違うわけですからね(笑)。
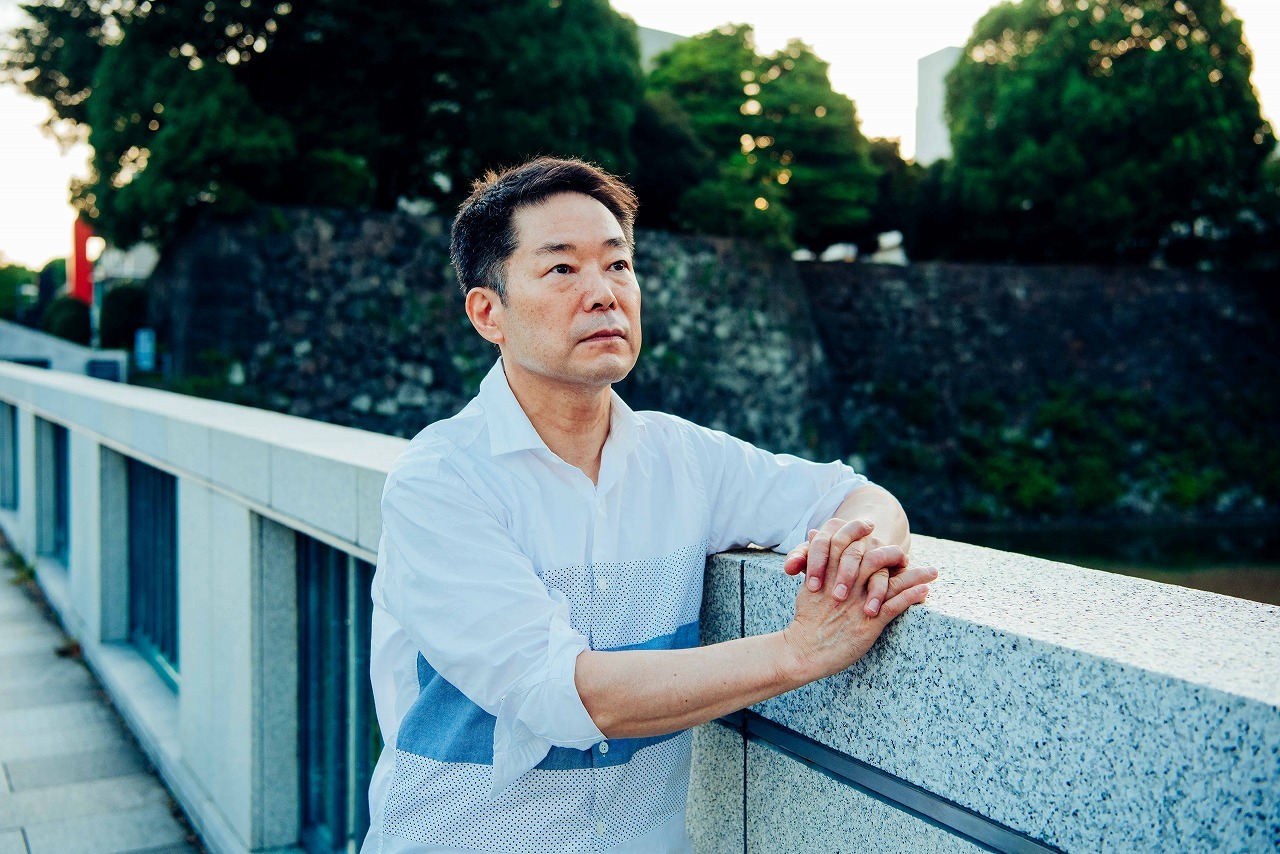
林英哲
弟子に引き継ぐ「モノクローム」
――休憩を挟んで、後半のステージでは英哲風雲の会が登場します。まずは、石井眞木さんが作曲された「モノクローム」が取り上げられますが、林さんはこの曲の世界初演(1976)に携わっていらっしゃるのですよね。
この曲の初演では、台、スティック、フォーメーション、所作なんかを全部自分で工夫して作ったんです。それを見た外国のプロの打楽器奏者がものすごく感動して「あれは譜面があるのか?」と言われました。実際の譜面を見せても「あなたがたの演奏はこれをやっているようにははとても思えなかった」「あれは東洋のマジックかなんかで、指揮者もいないのに突然全員バシッと揃ったりするのは、どういうやり方で練習するんだ」と、ものすごい食いつかれて(笑)。作曲者の石井さんも亡くなる直前に「モノクロームは英哲さんがいたから出来たんだよ」っておっしゃってくださり、有り難かったですね。
――この作品はこれまで相当な回数、演奏なされていますよね。
僕自身は数100回以上やっていると思いますが、弟子たちはしょっちゅうやる曲ではないんです。そもそも、これは集団時代の委嘱作品だから、それをソリストになってからもやるというのは掟破りだなと思って、その後石井眞木さんがお亡くなりになる20数年間封印していたんです。でも弟子たちはこの曲のことを知らないし、経験もないことに気付いた。
僕は初演からやっていたのに、これだけの名曲を弟子に伝えないのは問題かなと思って、その後世田谷パブリックシアターの公演(演奏活動40周年記念 林英哲コンサート2012『五輪具─あしたのために─』)で取り上げたんです。そしたら、色んな音楽関係の方が「どうしてこんなに良い曲を封印してたんですか?」「もっとやればいいじゃないですか!」と、皆さん昔のものをご存知じゃなかったんだなと気付かされました。弟子のためにも引き継ぎの意味もあってやるんです。

林英哲
――プログラムの最後には、林さん自身が作曲された「七星(しちせい)」が控えています。
これは英哲風雲の会にとって出発の曲なんです。煙草のセブンスターのテレビコマーシャルで僕が音楽をやっていたんですね。3年目に煙草の広告規制が段々厳しくなってテレビコマーシャルはこれが最後。だからお金がかかってもいい……そんな凄い太っ腹企画だったんです。それで、大太鼓を13人並べるという大変な曲をやることになり、打ち手を全国からオーディションで集めたんです。出来るだけ、がたいが良い打ち手でやろうっていうんで、みんな筋トレして筋肉をパンパンにしてやりました。
CMだから30秒だけの曲だったんですけども、大好評なので上演できるようにしようってことで書き足して、長いフルバージョンを作ったんです。大太鼓だけがあんなに沢山並ぶ曲ってないですから、あちこちで喜ばれましたね。それを見た若いメンバーが「入りたい」って来るようになってドンドン広まっていった。
――林さんご自身の活動にとっても、大きなターニングポイントになった曲だったんですね。
大きかったですね。それまで僕はずっとソリストでやるつもりだったから、まさか弟子をもったり、弟子のアンサンブルを作って一緒にやるようなことになると最初は思ってなかった。そして、この曲をサントリーホールでやるのは初めてなので僕自身も楽しみにしています。
――林さんからすると、サントリーホールという会場にどのような印象を持たれていますか?
有り難いことにサントリーホールは打楽器に向いてますね! そしてサントリーといえば、20歳の頃にグループ(佐渡国鬼太鼓座)を立ち上げるとき、最初に太鼓を提供してくださったのがその当時サントリー株式会社の社長だった佐治敬三さんで、大太鼓の胴に「サントリー寄贈」と書いてあったんです。佐治さんのあのスポンサードがなければ、我々のグループは出発できなかったんです。音楽専門ホールがないから佐治さんがサントリーホールを絶対作りたいと、そういう思いがこもったホールだから、あそこでやるのは特別な感慨があります。

林英哲
何を目指せばいいかを示せるコンクール
――さて、少し話は変わるのですが、昨年から「林英哲杯 太鼓楽曲創作コンクール」を開催されていらっしゃいますね。昨年(第1回)の総評で、和太鼓への取り組み方について、厳しくも愛のある言葉を語っていらっしゃるのが強く印象に残りました。このコンクールを通して、どんな「あした」を見据えていらっしゃるのかをお聞かせいただけますか?
和太鼓奏者になりたい、ソリストになりたいといったような人が出てくるようにはなったんですけれど、太鼓打つのは上手くても1人で一晩コンサートのことを出来るようになるっていう人材はなかなか出てこないんです。なかなか難しいですね。
和太鼓奏者が普通のミュージシャンとは違うのは、ダンサーではないけれど、打ち手の動きを見せるという要素も大事で、海外に行くと、その日本人の所作とかお辞儀の仕方とか、キチッとしている感じを皆さまが喜んでくださるんです。
日本人はアフリカ系の人やヨーロッパ系の人に比べると手足も短いし、身長も低いですよね。その形を活かすには、日本人の伝統の中にあるような動きをきちっと取り入れて、自分でこなせるようにならないと太鼓打ちも海外に出て「日本の太鼓です」っていうときに説得力をもたない。せっかく底辺が広がったわけだからレベルアップのために、そういうような考えも含めて、新しい作品作りを試みさせて、評価するコンクールが必要だと思ったんです。
――それまでは、そういったコンクールがなかった。
これまでも色々なコンクールがあったようなんですけども、それは太鼓の経験のない審査員が評価するという、よく分からないコンクールが多かったようです。衣装をパッと脱いだのが格好良かったから点数が上がるとか、お客さんの拍手が多かったから点数が上がるとかね。それだけじゃ、その人たちは1位と2位の違いが何かってことが分からないわけじゃないですか。2位の人は、どうすれば1位になれるのかも何も示されないわけですけど、これはコンクールとしてはおかしい。意味がないと思うんです。
ちゃんと順位に入れなかった人にも全部講評をして「あそこはよく頑張っていたと思う。ただ上に入れなかったのはここをもうちょっと練習して、こうすれば君はもうちょっとレベルが上がるよ」と具体的に言えば、みんな練習目標が分かるわけですから、次は上がれるかもしれない。全員がお互いの演奏を見て、どうすれば向上するか、どういう練習をすればいいか、何を目指せばいいかを示せるコンクールをやりたかった。
僕の目が正確かは分からないけれども、自分はこういう仕事をずっと続けてきてその現場を全部知っているから、他に適任者がいないんだったら自分ひとりが講評するということでやってみようという風にしたんです。

林英哲
――そういう状況になってしまったのは、教育体制が整っていないということもあるのでしょうか?
伝統芸能の世界ではちゃんとメソッドがあって、テキストもあって、段階を踏んで学習していくとプロとしてやっていけるシステムがありますよね。残念ながら、我々のものは郷土芸能出発だし、新しく作ったものなんで、そういう土壌や背景がない。だからテキストもメソッドもないし、指導法もみんなマチマチ。郷土芸能としては、それでいいと思っていたんです。福井は福井、北海道は北海道。沖縄は沖縄のやり方があって、それを良いの悪いの言ってもしょうがないじゃない。そうすると、個性豊かな地域性のあるものが生まれるだろうから。
ところが、いまの時代というのはネットを通じてすぐに映像が手に入るので、どうしても均質化が進行するわけですね。北海道だろうが、何だろうがみんな同じようなことをするようになって、目指す方向や表現の形も似たり寄ったりになってしまう。地域性なんかあまり無くなってしまう。
――せっかくの個性が潰れてしまうんですね。
クラシック音楽の場合はメソッドがあり、そういうノウハウがあるから全く文化の違うアジアの日本みたいなところでも、これだけの完成度の高い音楽や演奏家が生まれるようになって、音楽大学もこれだけあって……。でも外国から見ると、それがすごく不均衡に見えるわけですね。日本の音楽大学は西洋音楽を教える大学で、日本の音楽を専門に教える大学はひとつもないですっていうと非常にビックリされるんです。日本へ勉強にいきたいという人が出てきて「日本のどこに行ったら教えてもらえるんですか?」と聴かれても「日本にはそういう教育機関がない」って言うと「え~っ!?」って驚かれます。
それが不均衡だっていう意識が我々のなかにあまりなくて、結局のところ明治時代に西洋先進国の文化を取り入れるっていうシステムがそのままなんです。もし太鼓が地域性を超えてやれるようなことになってしまったのであれば、今度はきちんとしたメソッドが必要になる。地域性を超えた新しいスタイルの太鼓のきちんとした指導法や、プロになるための教養も含めて技術的なことも含めて指導できる指導者がいないと、みんな見よう見真似からいきなりプロを目指すことになってしまう。そこの落差を埋めるものがないんです。
――なるほど。言われてみればその通りです。
このコンクールは、僕の太鼓学校ではないけれど、そこを少しでも埋めるものにしたい。みんなが少し気がついて目を開いてくれるようなものが出来ればいいなと。ずっと「ドンドンドンドン」叩いていれば、お客さんが途中から拍手してくれる。確かにそれもいいんだけど、でもそれだけでは表現としてそれ以上のものにはならない。
例えば、その瞬間の受け狙いで作ったような曲でも、海外でそれなりに受けるんです。日本週間とか、日本フェスティバルみたいなところにそういう人たちが行って「僕達もニューヨークでやりました」「パリでやりました、すごい喜ばれました」と言います。けれど、僕のところにこの間もドイツから「林さんの練習を観に行きたい。稽古場に行かせてもらえるだろうか?」というメールが来たんです。見学に来たい理由が書いてあって「ドイツには日本から沢山太鼓のチームが来るようになりましたけど、あれはみんな"Fire Work"(花火)です。林さんはどう見ても、それとは全く違うことをやっている。どうしたら林さんのようになれるのか、どういう練習をしているのかを見てみたい」と言うんです。
――その時、一瞬だけの作り物と、本物を見極める目を持っている。
面白いのは、海外の人のほうがそういう目を持ちますね。筑波大学でも年に1度指導するんですけれど、留学していたアルゼンチンの学生が僕のところに習いに来ているんです。僕が伝統的なスタイルと違うことを授業でも言っているから彼も分かっています。でも「英哲先生がやっていることはオーケストラとやってもジャズピアニストとやっても、どういうシチュエーションとやっていてもちゃんと日本のものをやっていると思える。他にも太鼓をやる人はいるけど、あれは日本の太鼓ではないです」って彼が言うんです(笑)。「僕はアルゼンチンに日本文化センターを作りたいです。ちゃんとした日本のものを伝えるようにしたいです。」っていうから「お前は偉いねえ」って(笑)。思わぬところから、ちゃんと見ている人たちもいるんだなと。
――和太鼓なのに国内の受容状況が育っていないということなんですね。
面白いのは海外で我々の公演を観た日本人は、すごく喜んでくれるわけです。例えば、僕のオーストラリア公演に日本人留学生が現地の友達を連れて観に来ると、本当にビックリするんですよ。要するに、海外に留学するってことは日本の文化より外国に興味があるから、英語の勉強したりとか来ているわけですよね。日本のものなんか見たこともない。
でも我々のパフォーマンスを観ると、自分が日本人だって目が覚めるんですよね(笑)。楽屋に来て「僕は日本でこういうのに全く興味がなかったし、観たこともないんですけど、今日は本当に日本人で良かったなと思いました」って言うんです。それは日本人のパフォーマンスを現地の外国人が、大スタンディングオベーションでみんなから日本人が賞賛を受けているということを外国で見ると興奮度がすごく違うみたいで。
国内にいるとそういうことが分からないですよね。そこがなかなか伝わらないので、どうしても温度差がある。日本の人が悪いとかじゃなくて、こういう分野はしょうがないかなとも思うんですが……。そういう状況が40何年、ソリストになって35年ですけど、ずっと続いていて、あんまり結局変わってないんですよ(笑)。

林英哲
現代人には難しい「裸足」の感覚、そして「美しい誤解」
――思わず色々と考え込んでしまいますね……。林さんは他のインタビューで、日本の太鼓について『究極的に言い切るなら、精神面でも実技面でも「裸足で立っているかどうか」』とおっしゃられていましたね。このことに、どのように気づかれたのでしょうか?
指導していると、僕が自然にやっていることが出来ない人たちがいることに気がついたんです。トイレも洋式になり、家でもご飯食べるときは椅子に座ってご飯食べますよね。だから「正座」とか「しゃがむ」とか、全く出来ない子どもがいる。音大に来てる子なんか、特に出来ない(笑)。股割りして、お相撲さんみたいに四股(しこ)踏んでみたいなことはやったことがないんです。
外国の人に太鼓を教えると、一番のウィークポイントが膝なんですね。オランダ人の打楽器奏者に太鼓の打ち方を教えたんですが、打楽器奏者だから手は一応リズムは叩けるんですけど、足が途中からフラフラして(途中から)保てなくなる。日本人や東洋人は足が短いこともあるんですけども、ああいう格好がある程度自然に出来るんです。日本人はああいう形が似合う体型だし、日本人が美しく見える体型だなと。
――確かに日本人の構えの姿勢はビシッと決まりますね。
でも、今の若い人はその経験がなくて出来ない。特に女の人は、ハイヒールで完全に足先がすぼんでますから、踏ん張ってといっても全く出来ない。「足を踏ん張って」といっても、構えが全然落ち着かない。これは、裸足で重心を低くして踏ん張るという日本人の生活にかつてあったものが今なくなっているからなんです。
そして考えてみると、お能や歌舞伎、相撲や剣道や柔道や、日本のものは大体、裸足や足袋で、くつを履いていない。特に剣道や柔道や相撲みたいな格闘技系のものは、日本人は必ず裸足になるんですけど、韓国のテコンドーもモンゴル相撲も全部くつを履くんですね。ブルース・リーだってカンフーシューズを履いているんです(笑)。
日本文化が、アジアと似ているようだけれども完全に違うのは「裸足になる」「しゃがむ」「正座する」っていう部分で、ここが基本になると思ったんです。ところが地域の太鼓なんかの練習を見ていると、みんなスニーカーを履いて教えている。それで、裸足ということを特に強調して言うようになったんです。

林英哲
――面白いなと思うのは、林さんは郷土芸能の伝統を引き継ぐのではなく、自ら新しいスタイルを確立していかれたわけですが、日本的なるものとは何かという部分については伝統を強く意識していらっしゃるのですよね。
皆さんね、悪意ではない見方なんでしょうけども、何となく地域伝統の郷土芸能に毛が生えたようなことをやっているという風に思われるんです。「太鼓は日本人の心ですねえ」って言われたりもするんですけど、いやいや昔の日本人は、太鼓にそんなに思い入れはなかったんですよと(笑)。そういうのを「美しい誤解」って僕はよく言うんです。
でも、面白いのは郷土芸能でもレベルの素晴らしいものとそうでないもの。そういう比較は難しいんですけども、僕から見て優れた郷土芸能というのは、必ず当時プロが指導したんだというのが分かるわけです。こんなにレパートリーやバリエーションがあるものを、兼業しながら作ったとはとても思えないんです。
――明らかに専業でやっていたプロの手が入っているということですね。
そう、絶対に。芸能のプロでないとこんなことは出来ないよというようなものが残っているわけです。我々は郷土芸能って自然と出来上がっていったものだろうと思ってるけど、そうではなく時代時代の目利きがこさえたものが今の郷土芸能なんじゃないかと。おそらく中世も江戸時代もみんなそういうことが行われていた……そういう感覚が僕のなかにあるもんだから、現在の事情にあわせた新しい太鼓をプロが指導して新しく作っても別に問題はないじゃないかと思うんです。
――本日は色々と興味深いお話お聴かせくださり、本当に有難うございました。最後に改めて、公演にいらっしゃる皆さまにむけて一言いただけますでしょうか。
何年かおきにこういうのをやらせていただいているのですが、でもまだ一般の人は「サントリーホールで太鼓を使って何をやるんだ?」みたいな感覚もおありだと思うんです。別に僕が35周年だなんだっていうのを看板にしてるんじゃなくて、響きの良い音楽ホールで音楽として太鼓を聴くっていう体験を是非! 空席が出来るぐらいならタダでも入ってもらいたいぐらい(笑)。それで目からウロコが落ちますから是非、聴いていただきたいというのをお願いしたいと思います。
インタビュー・文=小室敬幸 撮影=髙村直希

