演出家・江間直子に聞く──無名塾公演『ベルナルダ・アルバの家』

無名塾公演『ベルナルダ・アルバの家』(フェデリコ・ガルシア・ロルカ作、江間直子演出) 写真/小嶋雅人(tendotFive.)
無名塾の稽古場「仲代劇堂」で、フェデリコ・ガルシア・ロルカ作『ベルナルダ・アルバの家』が上演中だ。スペインのアンダルシア地方の名家で、夫の死により8年間の喪に服することになった妻と5人の娘たちを描くロルカの代表作だが、この舞台は、40年以上の歴史を誇る無名塾にとって、初めての女性だけによる上演なのだ。無名塾にも新しい風が吹こうとしている。初めての試みを実行している演出家の江間直子に話を聞いた。
仲代劇堂での「稽古場公演」
──無名塾の仲代劇堂における「稽古場公演」は、今年2月に上演された『かもめ』が最初ですか。
「稽古場公演」と銘打った公演は『かもめ』からかもしれませんが、約15年前から、年に1度くらいのペースで公演しています。「秘演」とか「無名塾小さな演劇祭」と呼んでいた時期もあります。
──では、『かもめ』から体制が変わったんですね。
わたしが演出をしたことと、チラシのデザインがこれまでのものとは変わりました。広く宣伝するように努めています。
──新体制の「稽古場公演」としては、チェーホフの『かもめ』、ロルカの『ベルナルダ・アルバの家』と続くわけですね。有名な古典を演目として選んだ理由はありますか?
どちらも好きな作品であることが大きな理由ですが、そこに登場する人たちが立派じゃないところが好きなんです。そのなかの人間くさいところを描けたら面白いと思って、こういう流れになりました。
──ロルカは『血の婚礼』『イェルマ』『ベルナルダ・アルバの家』と3作書いていますが、そのなかから『ベルナルダ・アルバの家』を上演しようとした理由を教えてください。
『血の婚礼』と『イェルマ』の2本は、どちらかというと韻文で、詩のような作品。それに対して、『ベルナルダ・アルバの家』は散文で書かれています。今回は女性だけの芝居を上演したいと思ったから、この戯曲を選んだんですが、すごく人間くさく、女性くさいものを戯曲から感じます。
──ロルカは女性の描写がすごくうまいですね。
そうですね。ロルカは同性愛者だったし、女性といっしょにいることが多かったせいかもしれません。
昔、ロルカの親戚の家が、この戯曲のモデルになった家と井戸を共有していて、井戸のところまで来ると、家のなかの話がまる聞こえだったらしいんです。ロルカは井戸に隠れたまま、それを全部メモした。そういう言葉から構成されているので、リアルな台詞になっています。だから、頭で考えただけで出てくるような言葉じゃない、すごく生きてる言葉だなと思います。そういう面白さもあります。
女性だけの上演へのこだわり
──女性だけの芝居を上演したいと考えたのは、どうしてですか。
無名塾では女性だけの公演がありませんでした。必ず、仲代(達矢)さんが、なかにいらっしゃる。そこで今回は、女性だけで上演したいということから始まりました。全部を女の人のものにしたいと思って『ベルナルダ・アルバの家』を選んだんです。
──先ほどおっしゃった、井戸のところでロルカが女たちの話を聞いていたというエピソードはすごく印象的で、なぜかというと、劇中で母親のベルナルダが「川もない、井戸もない、呪われた村に住んでるんだから」と語る台詞があります。つまり、水がぜんぜんなく、乾燥した土地で起きている出来事を、実際には井戸のあるところで聞いていたのが面白い。
舞台になった村は、アンダルシアのなかでも、ものすごく乾燥した場所らしいです。まわりを山に囲まれた、陸の孤島みたいな感じの土地です。
──乾燥して、いくぶん隔絶された場所だからこそ、湧きあがる物語という印象も受けます。水分が枯渇している環境とは対照的に、女たちが血を滾(たぎ)らせていく。ところで、『ベルナルダ・アルバの家』には、3つの世代が登場します。60歳のベルナルダを中心に、幽閉されたお祖母さんのマリーア・ホセファ、そして5人の娘たち……20歳のアデーラから39歳のアングスティアスまで、全部で5人いる。さらには、そこで働く女中たち。そのように女性性が、いろんな世代から確かめられていきます。ある意味、残酷な面もあるような気がします。
残酷……(笑)、20歳のアデーラは、将来、このお祖母さんのようになるかもしれないという残酷さですね。このお祖母さんがいたからこそ、ベルナルダの性格ができあがったんだと思います。すごく厳粛な、あれもこれも駄目で自由にさせない、外にも出させない。
──ベルナルダは鉄の規律で縛ろうとします。
たぶん、お祖母さんがいるから、そのような規律を保たないと、この家は狂ってしまう。だから、ベルナルダは娘たちを押さえつけていく。でも、娘たちへ愛情のかけかたが、それぞれ違っています。結婚させようとする娘もいるし、結婚しなくていいと最初から決めつける娘もいる。残酷な感じはあまりしませんでしたが、わたしとしては、女性のそれぞれの段階の悩みが見えるところが面白い。
──程度の差はあれ、娘たちは希望と失望の両方をまだ持っています。
いちばん年下のアデーラは、まだ挫折を体験していないので、目の前が開けてて、困難にぶつかっていく力がある。その上のマルティーリオは、体が不自由なので、わたしにはできないと思いつつも、アデーラのようにふるまいたい気持がある。真ん中のアメリアは、姉たちと妹たちの様子を見て、自分の立場を決めようとする。その上のマグダレーナは、きっと亡くなった父親に近い立場にいて、母親と権力争いをしていたんじゃないかと。
──マグダレーナは、亡くなった現在の父親にとっての最初の娘ですから。長女のアングスティアスだけが、前の旦那さんの娘になりますね。
そういった権力争いもあり、父親が亡くなったので、ちょっと自暴自棄になっている。アングスティアスは39歳で初めて恋人ができて、ちょっと浮き浮きしてる。
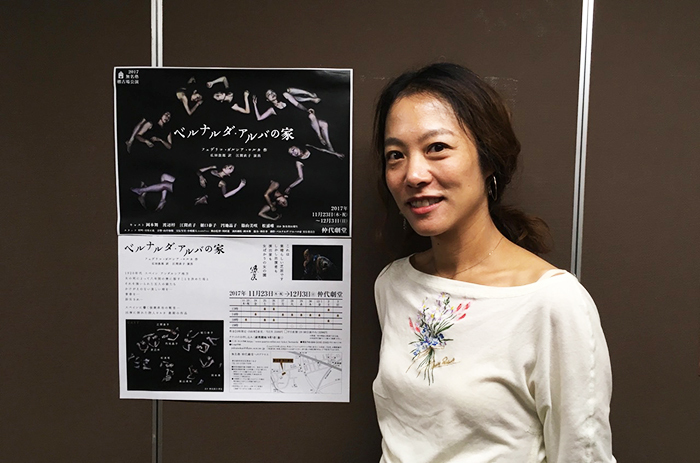
演出を手がける江間直子。
子宮で考え、子宮で話してほしい
──第1幕は父親の葬儀から帰宅したところ、第2幕は喪に服す時間、第3幕はそれまで表に現れなかった嵐が一気に噴出する構成になっています。本音と建て前がものすごく、その場にいない人物については辛辣に語る場面もありますが、上演にあたって演出上の構想はありますか?
わたしが稽古場で、いちばん最初にお話しをしたとき、「頭で考えて話すのではなく、子宮で考えてほしい、子宮で話してほしい」と言いました。子宮が何を考えているのか、わたしはいまでも把握できないんですが、わけのわかんない感情や意見が出てくるんです。子宮は女性にしかないものですし、本当に子宮から出てくるものでお芝居を作りあげたいと思っています。
──理屈ではなく、身体的な、女性のなかから湧きあがるもので、『ベルナルダ・アルバの家』を構成してみたいと。
本当に舞台全体に流れるものとして、それがほしい。
──子宮という感覚が面白いですね。子宮は腹痛を伴って暴れることがあり、身ごもることもあり、ときには、存在を忘れるほどおとなしくしてるときもある。たとえば、第2幕では、家族が長い喪に服するんですが、かつて五月舎が上演した鵜山仁演出の舞台では、裁縫をしたり、ミシンをかけるシーン、姉妹たちのやりとりがすごくきれいでした。当時、ミシンがすでに使われていたかどうかはわからないんですが……。
1920年代が舞台なので、すでにあると思います。
──もう約30年前の舞台ですが、いまでも記憶に残っています。
それはすごく重要なシーンだと思います。『ベルナルダ・アルバの家』は悲惨な結末を迎えますが、それだけにはしたくない。どろどろしたものだけを見せるようなお芝居にもしたくない。女たちは押し込められた場所にいるけれども、それでもみんな生きようとしているし、幸せをつかもうとしている。そういう女たちを描きたい。なので、姉妹だけでしゃべっている場面や刺繍をしている場面が重要な鍵になると思います。
──日常がそこに積み重なっている。喪に服する時間は、女たちはずっとそうしてるわけだから。それがとてもすてきに見えました。
カンタフォンテと写実的ドキュメンタリー
──tptが門井均演出で上演した『ベルナルダ・アルバの家』では、音楽が大きな役割を果たしており、舞台袖でギターの生演奏に合わせて男女が歌い、その声や拍手のリズムに合わせて、登場人物たちがどんどん高揚していきました。音楽で考えていることはありますか。
カンタフォンテはご存知ですか? スペインのフラメンコのカンテよりも、少し前の言い伝えを伝承するための歌です。日本だと、カンテが演歌としたら、カンタフォンテは民謡ぐらいの感じ。「フォンテ」は「本物の」「元の」といった意味で、お経みたいな歌なんですけど、ロルカがカンタフォンテの優れた歌い手を集めようと呼びかけ、大会を開いたと聞き、そのカンタフォンテの歌が使えたらと思っていましたが、実際には使いませんでした。
──『ベルナルダ・アルバの家』は、冒頭に「この三幕の劇は写実的ドキュメンタリーとして意図されたものである」と書かれています。これをどう考えていますか。
いま、舞台を三方囲みにしているのは、実はそういう意図もあります。いわゆる演技ができない空間になっていて、本当に感じて、そこで生きないと、すべてがバレてしまう。
──観客の方向を意識して演技するのではなく、どこから見られてもだいじょうぶなように……。
自分のなかに人としてちゃんと動いているものがないと、立っていられないと思うんです。わたしは「写実的」よりも「ドキュメンタリー」に重きを置いたんですけど、本当にそこにいて、生きていることをみんなができれば、写実的な部分、ドキュメンタリーな部分もできるんじゃないか。これは簡単なようですごく難しいし、本当に何度も追求して、そこにいたるという……。
──観客は、眼前でおこなわれている出来事を、こっそりと覗くような感じになるんですか。
三方に座る観客が、壁の役割でもあり、世間の目の役割でもあると思っていて、どこかの居間を覗き見している感覚になれたらいいなと……。
──あるいはロルカがしたように、井戸のところで聞いているような(笑)。
そういう感覚になれたら、いちばん面白いなと。
女性への抑圧と時代の空気
──全篇を通して、娘たちが父親の喪に服することを強要され、抑圧されている印象も受けます。上演に際して、いまの女性たちに対するメッセージはありますか。
実際に、女の人は仕事と家庭とで男性の倍は働いているし、いまでも家のことは女がやるものと思われています。
抑圧については、空間的に閉鎖されていることだけではない、たとえば、年齢的にあなたはもう結婚できませんと言われた場合、そんなこと関係ないとはねのければいいんですが、その人自身にもそういう壁があり、自分はできないと思い込んでしまうとか……。
──世間とか社会的通念ものが、無言の大きな圧力になって乗っかってくる。
『ベルナルダ・アルバの家』の上演を決めたとき、劇中の抑圧されて自由に話せない状況が、いまの日本にちょっと似ていると感じました。実際に、ロルカもこの戯曲を書いた2カ月後に暗殺されています。労働者を擁護する活動をしたり、ジプシーが素晴らしいと発言していたために、捉えられて暗殺されてしまった。
そういう状況があって、いまと似てる感じがすることもこの戯曲を選んだ理由のひとつです。だから、この女性たちが抑圧されているのは、「家から出るな」と言われるとかだけじゃない、社会的な圧力も感じます。そういったものにつなげていけたらと思っています。
──では、最後に、演出家の考える見どころについて聞かせてください。
無名塾のお芝居は仲代さんを中心にしていましたから、男性が必ずいました。でも、今回は本当に女性だけ、男性はひとりも登場しない。声ぐらいしか出てこないというお芝居は初めてです。いろんなタイプの女性、いろんな世代の女性が見られるのが、見どころのひとつかなと思います。
それに加えて、先ほど言った、いまの空気とちょっと似ている、何か通じるものがあると思うので、そういうものを感じられるお芝居にできたらいいなと思います。
取材・文/野中広樹
■作:フェデリコ・ガルシア・ロルカ
■訳:広田敦郎
■演出:江間直子
■日時:11月23日(木・祝)〜12月3日(日)*12月3日(日)のみ売り切れ。
■会場:用賀・仲代劇堂
■出演:岡本舞、渡辺眸、江間直子、樋口泰子、円地晶子、篠山美咲、松浦唯、無名塾31期生