長塚圭史、劇団化した「阿佐ヶ谷スパイダース」と、新作『MAKOTO』を語る
![長塚圭史(阿佐ヶ谷スパイダース) [撮影]吉永美和子(人物すべて)](https://spice.eplus.jp/images/mwUgUUFf2yJhvY1o6Odh7irQd6y9cPdrAZrWl28Coy91xLCoc5iw2dLVY3ShlDS8)
長塚圭史(阿佐ヶ谷スパイダース) [撮影]吉永美和子(人物すべて)
「今までと違う創作の場、違う視点の劇を、ここで作っていきたいです」
1996年の旗揚げ以来、長塚圭史・中山祐一朗・伊達暁のプロデュース集団として活動してきた「阿佐ヶ谷スパイダース(以下阿佐スパ)」。それが2018年から、10人以上の役者・スタッフを加え、「劇団」として再出発することになった。メンバーたちが大きなプロデュース作品に出る機会が増えたことにより、その差別化を図るためにも、あえて演劇の原初的な形式といえる「劇団」での活動継続を選んだ阿佐スパ。主宰で作・演出の長塚圭史に、劇団化に至った経緯と現在の未来予想図、そして新生阿佐スパの船出となる『MAKOTO』について語ってもらった。
■「解散だ」と思った所から、一つの祭を形成しようとする「村」に。
──劇団として再出発してから半年が過ぎましたが、現在の状況はいかがですか?
やることがいっぱいあって大変ですね。今回の公演も、僕が各劇場に「公演させて欲しい」と直談判しに行ったし、チラシの折り込みにも行きますし。でもそうするとみんな「長塚、これも自分でやるんだ」って感じで、ちょっと前のめりになってくれます(笑)。
──阿佐スパは、若い表現者が劇団ではなく「ユニット」を結成するようになった、その先駆け的な存在でしたね。
その前に劇団をやってたんですけど、どうしても劇団の中で(役を)回さなきゃいけないことに、やっぱり限界を感じたんですね。そんな時に関西の俳優から「売名行為」(注:80年代に関西で活動していた演劇ユニット)の噂を聞いたんです。固定メンバーは3人だけで、他の人たちは公演ごとに集めてくると。舞台は観てなかったけど、その話だけ聞いて「それは理想的だなあ」と思って、中山と伊達と始めたのが阿佐スパだったんです。
──作家としては、脚本を書く時に俳優の人数や年齢層に縛られない。団体のリーダーとしても、劇団にありがちな人間関係のわずらわしい問題に悩まされないなど、当時はかなり画期的な集団スタイルでした。
それと公演ごとに新しい風が入ってくるわけだから、非常に面白いし、飽きないに決まってますよ。パルコ(・プロデュース)で仕事をするようになった頃は、何かカッカッカッという熱があって、ちょっとずつ調子に乗って。もうどんどん面白い芝居をやって、受けて、ワーッと酒飲んでって……若かったですよね(笑)。それで何かを見失ったわけじゃないんですけど、やっぱり年齢を重ねていくに連れて「これを続けていくことで、果たして次の展開があるのか?」って考えるようになって。実は『はたらくおとこ』再演(2016年)直前には、本当に先が見えなくなって「もう解散しかない」と思ってたんです。

阿佐ヶ谷スパイダース『失われた時間を求めて』(2008年)より。左から長塚圭史、伊達暁。
──そこから一転して、劇団化という話になったのは?
3人で解散の会議をしてる時に、『蛙昇天』(2015年)のことを思い出したんです。それは僕ら3人が仙台に住み込んで、地元の方たちと一緒に芝居を作る企画だったんですけど。その時の、みんながすごく近い距離で芝居を作っていく手作り感と、「今日のご飯どうする?」って言い合うような、生活と密着しながら作る過程がすごく良かったなあって。それで「こいつらと別れる必要はない」と考え直して。儲かる儲からない関係なく、ただ「面白い劇を作りたい」と思ってる人たちと劇を作る体験がもう一回できるような、今までと違う集団を再構築できないか? という話になったんです。
──それが「劇団」という形だったと。
今までの阿佐スパのように、(公演前後の)3ヶ月ぐらいの中で関係性が終わるのって、他の(プロデュースの)舞台とやってることは同じなんですよね。これはこれで面白いし、お客様のためにもいいものだと思う。ただそれとは別に、10年後に「もっと難しい題材を相手にしたい」と思った時に、一緒に自信を持って向かえるようなチームを作っておきたいと。それは田中哲司さんと(葛河思潮社の)『浮標』(2011・2012・2016年)を繰り返し上演することで、どんどん劇が強くなっていったという、積み重ねることの重要さを感じたことも大きかったです。
あとはやっぱり、手触りとか実感ですよね。僕らのやってる演劇って、すごく肉体のものだから、やっぱり身体がもう少し響き合わなきゃいけないと思う。ということを考えると、刹那的な関係だけじゃなくて、もっとつかみあえるような仲間を作りたい。そうすることで、芝居を始めた頃みたいに「公演を宣伝するのもバラシをするのも、全部が演劇的行為だ」という所に立ち戻ってみたかったんですね。完全に時代と逆行してるし「演劇の勝負の世界から降りるのか?」みたいなことを言われたりもしたけれど、そんな思いでやっていると何だか楽しいんです。
──阿佐スパの常連だった「猫のホテル」の中村まことさんや「ナイロン100℃」の村岡希美さんなどが、今いる劇団とかけもちしながら所属するというのもユニークですね。
まったくのゼロではなく、よく知った人たちと再スタートできるわけだし、そこに改めて若いメンバーが加わるわけですからね。きっと鮮度は出てくると思います。ここからさらに新しい人を増やして……それは新人を入れるだけじゃなくて、誰かベテランの人が「入りたい」っていうのもあると思う。今はスタッフを含めて(劇団員は)20人ぐらいだけど、それがどんどん広がって、大阪や博多とかでもクリエーションができるような展開にしていけたらなあと。
今の所、年一回公演を打つことは決めてますけど、必ずしも全劇団員に参加してもらうんじゃなくて、「やるよー」って言った時に手を上げた人たちと、その時どきで一緒に作るという感じです。「この舞台に出たいから、今年は休ませて」っていうのはOK。やりたい人だけ来て。ただし劇団員として、稽古以外にいろんな作業に参加してもらうし、一度決めたら勝手にやめないで……とは言っています。ただこれ「今までの阿佐スパと何が違うの?」と聞かれたら、意外とダメなんです(笑)。先を見据えるという意識的な問題で、僕としてはだいぶ違っているけど、その時やれる人たちと面白い芝居を作るというやり方は、以前と変わらないから。実際このゆるやかな関係に、とまどっている人もいると思います。
──従来の劇団ほどの拘束力はないけれど、各自に集団を維持する責任が生じているという点では、確かにユニットとはまた違うわけで。劇団でもユニットでもない「第三の何か」みたいな感じを、今受けています。
やっぱり「こうだ」って言い切れるものは、別にやりたくないわけですよ。今までにない、面白い集団を作れるかな? という風に模索して、いろいろ広げていきながら浮き上がっていけたら、自然と新たな状態を獲得できるんじゃないかと思っています。ただ僕の中では「お芝居をする前に、みんな一つの人間である」みたいな感覚があるのが、またずいぶん違っていて。僕はどちらかというと芝居バカだから、今まであまり考えてなかった、みんなの生活の事情……子どもがいる人のために、夕方には全部終わる時間割にしようとか、「一度みんなでバーベキューとかしなきゃダメかな?」とか(笑)。劇団員それぞれの生活や人間性を考えながら動くというのが、僕の中では今すごく新鮮なんです。
だから村ですよ、本当に。一つの作品……一つの祭を形成させようとしている村ができた所。来年以降もその祭を続けていけるように、その村をさらに良くしていけるように、村人の生活のことも含めて動いていくという。そのためにはどうすればいいかは、まだはっきりとはわからないし、いろいろと泣きつかなきゃいけないこともいっぱいありますよ。でもそんなのが、今すごく面白い。僕もう、面白がりたいだけなんです(笑)。もちろんそこにみんなを巻き込んでいる責任は取るけど、まずは自分が「面白い」と思える場所を模索して構築していきたいし、今は後ろ向きなことを考える時間すらもったいないですね。何はともあれ、まず10年はこの形で歩んでいけたらと思っています。

長塚圭史(阿佐ヶ谷スパイダース)
■僕個人が抱える問題が地球上で一番でかい、という観点で劇を立ち上げる。
──新作『MAKOTO』着想のきっかけと、現時点での内容は。
『はたらくおとこ』の前に、阿佐スパをやり直すことと、そこに中村まことさんが新しく入ることが決まって、「何かみんなを喜ばせることがしたい」という気持ちがあったんです。それで本番が始まって、(公演場所の)本多劇場まで通ってる時に、バーっとこの話の骨格が浮かびました。奥さんを亡くした男が、彼女のことを忘れるために、普通の常識では考えられない力を芽生えさせる……という。それでその日のうちにアイディアをまとめて、みんなに「どうだ!」って渡しました。だから劇団再編のエネルギーが書かせた作品、とも言えます。
中年の漫画家が、自分の奥さんの死の真相を探しつつ、彼女のことを一秒でも早く忘れるために、池袋や渋谷の街をとにかく走り回る。その姿はとっても狂ってて、(書いてる)僕もついて行けないぐらい(笑)。さらにそこに、オリンピックで大きく変容しようとしている、東京の都市の風景が交差していきます。一人の人間を忘れようとする時の体力や孤独、虚無感みたいなものと向き合う男の姿が、今の東京の街と重なっていく。と同時に、日本人の土地とか場所に対する、日和見的だけど確実に低層で流れている信仰みたいなものも、活用できたらと思っています。
──「忘却」に加えて「都市」も大きなモチーフになるんですね。
別に都市論をやるわけではなく、要は僕にとっては都市って故郷なんですよ。僕は渋谷で生まれ育って、今まさに渋谷駅周辺が大きく変わっていくのを見て、街には自分の思い出や、生きた時代が閉じ込められているということを、まざまざと思い返されたんです。人が生きるということは、その土地に生きているということだ、と。さらに、一人の人物を忘れようとしても、街の風景のあらゆる所には、つい思い出してしまう痕跡がある……人を忘れるには「街」を抜きにして語れない部分があるなあ、と思ったんです。
でもその「忘れる」ということ自体が、なかなか面白い。僕自身、一個のことを忘れようとして、狂ったようになったことがあって。でも今それを思い返すと、忘れるべき出来事よりも、忘れようとしている自分の状態の方が劇的だし、悲惨だし、面白いんですよ。で、その出来事の光景や匂いを一回抹消して、再構築して、冗談として語れるようになった時に「ああ、上手く行った!」と(笑)。今回は、そんな簡単に説明できちゃうことをやろうとしているわけじゃないけど、近い感覚はあります。
阿佐ヶ谷スパイダースvol.26『MAKOTO』トレイラー。
──先ほど言われた「常識では考えられない力」は、具体的にどのようなものになるんでしょう?
その見せ方を、まだ考えてる状態です。今って「MARVEL」の映画で、エネルギーの視覚化みたいなものがすごいから、それを劇でやるにはどうするのが面白いんだろう? と。これ以外にも「ん、これどうすんだ?」ってなる描写がいろいろあるんですけど、劇団員の中には舞台監督や大道具の人もいて、彼らもプライドがあるから(笑)、上手く具現化してくれるはず。そうやって「今は思いつかないけど、みんなが何とかしてくれるんじゃないか?」という安心感があると、台本が好き放題書けますね。
──チラシのあらすじには「愛国心あふれる漫画家」という言葉がありますが、昨今のナショナリズムに関することも描かれるんでしょうか?
最初はそれに寄って書いてみようと思ってたんですけど、今僕がそれを書くとダメになりそうな気がして飛ばしたんです。今回の登場人物を、そういう風にモノを見ている人間たちと会わせたり、話したりすることに、どうも格別な関心を抱けなかったので。
──以前長塚さんに取材した時、マクロな社会問題を語るのではなく、ミクロな人間関係から普遍的な事柄を浮かび上がらせる方がいい……と話していた記憶があります。その意味では、ナショナリズムというマクロな問題を題材にするのは違うのかな、と思いました。
そうかもしれないですね。マクロな問題は確実に存在するけど、僕らはバカだからそれが表面化するまで気づかないということに、僕の劇は寄っていると思います。『はたらくおとこ』も(パルコ・プロデュースの)『LAST SHOW』(2005年)も、僕の中では原発なんですよ。あれが本当に爆発するまで、僕らは生活の中に原発があることを意識しない。それがバン! と重なり合う瞬間に、以前はすごく興味があったけど、今の僕にはありきたり過ぎる感じなんですよね。
たとえば、今(取材をしている部屋の)扉の向こうで大殺戮が起こっているけど、僕らはそれに気づかず話してる……っていう発想で昔は作品を作っていたけど、そういう激しい事件を舞台上で起こしてお客さんを驚かせる、みたいなことが面白かった時代は過ぎてしまった気がする。だって今って、そんな殺戮事件ありそうですもん、実際に(笑)。

長塚圭史(阿佐ヶ谷スパイダース)
──となると、これからはどういう発想で物語を書こうと思ってるんでしょう?
うーん……今話したみたいなシチュエーションが、昔ならそのまま劇になったけど、今はこういうことを表現するのにもっと違う脳の使い方をしないと。だってもはや、それってリアルじゃないですか。僕の本質は変わらないかもしれないけど、今はリアルのもっと先に行きたいし、リアルとは違う視点を獲得したいと思っています。それで言うと、今回「都市」がテーマというのは、意外と大きいかもしれない。主人公の生活に道は関係あるし、店は関係あるけど、都市という大きな概念はあまり関係ない。そういう漠たる大きなものと、今自分が抱えている問題が、ちょっとずつ照らし合わされていくという。
でも僕が生きている以上、僕個人が抱えている問題はどんな問題よりも、地球上で一番でかいんです。ということの観点からしか、劇はなかなか立ち上がらなくて。その僕の問題が、現実にどこまで届くか、どこまで侵食できるか……それが破天荒になる理由なのかもしれないけど。幼稚ですよね、そこは(笑)。
──長塚さんが「自分でもなぜこんなこと思いついたかわからない」と言うほど脚本の歯止めが効かなくなることがあるというのは、それが理由の一つかもしれないですね。今回は取り分け、それを思い切りやってくれそうな感じが伝わってきます。
躊躇せずにやろうと、すごくわくわくしています。他所で芝居を作る時は、割と理知的にならざるを得ない所があるけど、劇団でそんなことしても仕方がない。バーン! とレールから外れなきゃ、やれない劇があってもいいんじゃない? って。それがいわゆる小劇場から飛び出してきた時代からやってきた、パワーみたいなもの。そこに今の若い子たちのエネルギーが重なり合えば、違う視点のモノができるんじゃないかなあと思ってます。そうなんですよ、結構バカになることが必要で。
──ちょっと乱暴に言うと、長塚さんにとって今の阿佐スパは「バカになるための場」ってことなんでしょうか?
本当に乱暴だけど(笑)、でもそういう要素もある。それはある。まことさんを始め、針を振り切れる俳優たちがそろってるわけだし。だからそこを大いに信頼して……戯曲で褒められようとは思ってないです。褒められなくていいから、なにかすごいものができればいいなあと思っています。
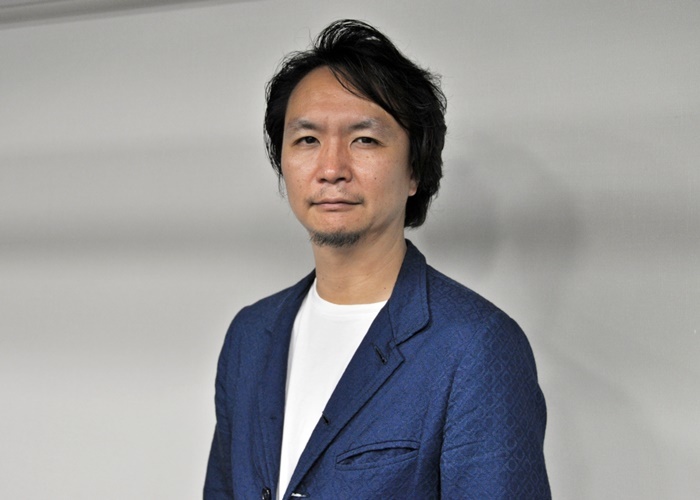
長塚圭史(阿佐ヶ谷スパイダース)
取材・文=吉永美和子
公演情報
【東京公演】
■日程:2018年8月9日(木)~20日(月)
■会場:吉祥寺シアター
【大阪公演】
■日程:2018年8月25日(土)・26日(日)
■会場:近鉄アート館
■日程:2018年9月7日(金)~9日(日)
■会場:KAAT神奈川芸術劇場〈大スタジオ〉
■日程:2018年9月1日(土)
■会場:りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館 劇場
■日程:2018年9月29日(土)・30日(日)
■会場:まつもと市民芸術館 実験劇場
■出演:中村まこと、大久保祥太郎、木村美月、坂本慶介、志甫真弓子、伊達暁、ちすん、中山祐一朗、藤間爽子、森一生、李千鶴
※藤間爽子は松本公演には出演しません。
